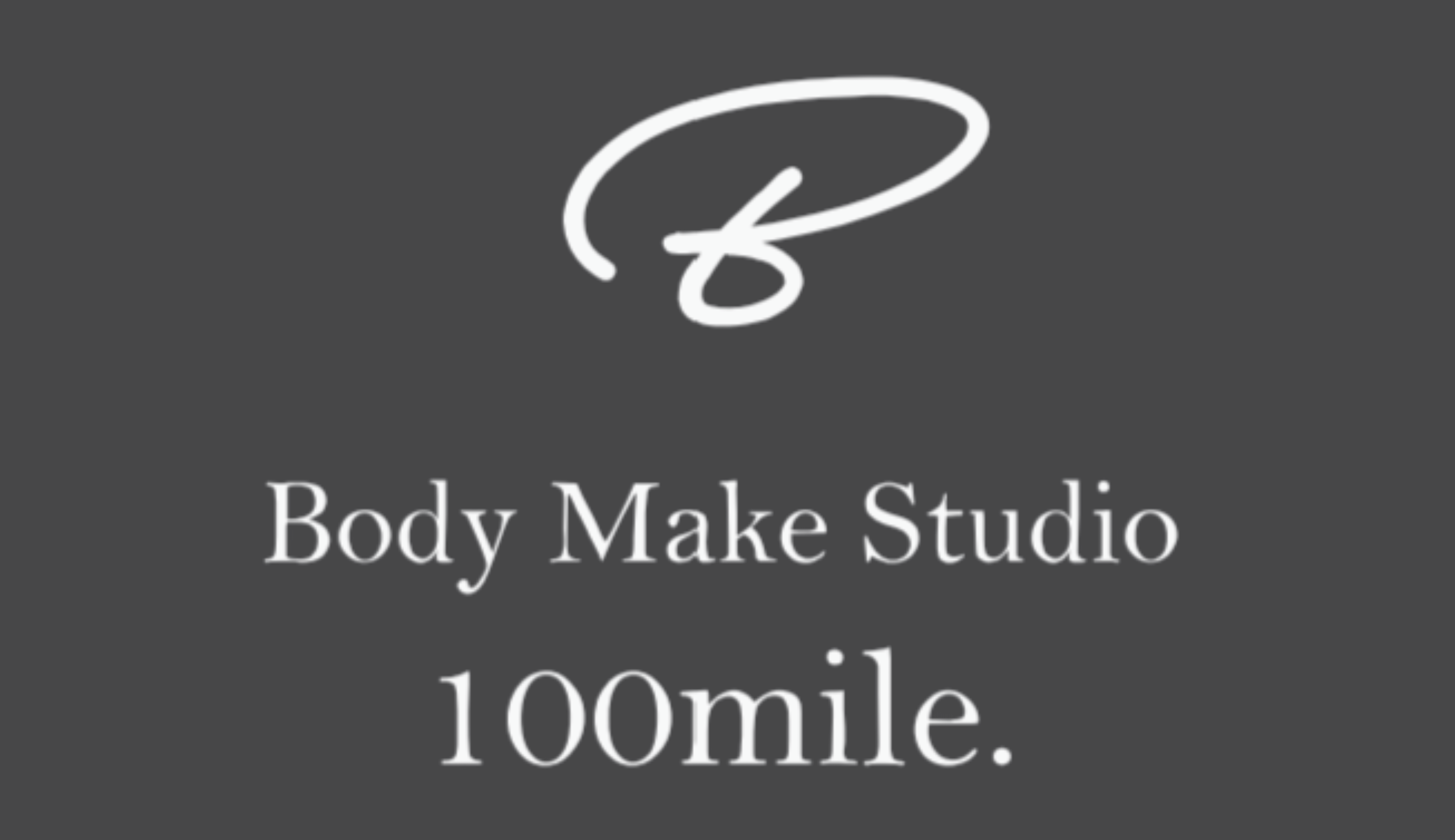皆さんこんにちは!BodyMakeStudio100mile.の後藤です!
今回の記事は中高年の方に向けた内容になります!
最近セミナーなどもたくさん実施していますが、その先々でお話しする方皆さん不調を抱えられていることが多く、特に多いのが参加者でなく主催の方に『不調が私自身あるんだけど、歳かな?』みたいなワードも良く伺います。
そして詳しくお話を伺うと多くの場合、その原因はストレスにありますが、調べていくと自覚のないストレスだったなんてことが大半なので今回はその『自覚のないストレス』についてご説明したいと思います!
それではどうぞ!
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?見えないストレスの正体 — 不調は脳の誤警報
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?なぜストレス社会の今、“不調”が増えているのか
現代社会は「ストレス社会」と呼ばれて久しい時代です。
仕事のプレッシャー、人間関係の摩擦、家庭内での役割の重さ、将来への不安。
特に中高年世代は、これらのストレスをいくつも抱え込みながら、
「自分はまだ頑張れる」「これくらい大丈夫」と、心身に鞭を打って日々を過ごしています。
ところが、その裏で静かに進行しているのが「原因のわからない不調」です。
病院に行っても異常なし。
血液検査をしても数値は問題なし。
それなのに、肩や腰の痛みが抜けない。
夜眠っても疲れが取れない。
集中力が続かない。気分が晴れない。
こうした状態を「年齢のせい」や「運動不足」と片付けてしまう方も多いのですが、
実はその背景には“自分では気づきにくいストレス”が潜んでいる可能性があります。
■「自覚できるストレス」と「気づけないストレス」
私たちは一般的に、ストレスというと「心の問題」を思い浮かべます。
たとえば職場での人間関係、仕事の締め切り、家族との関係など、
感情が関わる出来事をストレスと呼ぶことが多いです。
もちろんそれも大切な要因ですが、実はストレスにはもう一つの顔があります。
それが、「脳が無意識に感じているストレス」です。
人間の脳は、常に「自分は今、安全かどうか」を判断しています。
その判断材料になっているのが、体から脳へ上がってくる感覚情報です。
目で見た情報、耳で聞いた音、皮膚で感じる刺激、関節の動き、内臓の状態など
これらの情報がスムーズに脳へ届くことで、人は安心して動けるようになります。
ところが、この感覚情報のどこかが乱れたり、滞ったりすると、
脳は「何かがおかしい」「もしかして危険かもしれない」と誤って判断してしまいます。
このとき、脳の防御システムが働き、筋肉を緊張させたり、自律神経を乱したりして体を守ろうとします。
その結果として、肩こり、腰痛、頭痛、倦怠感、息苦しさ、
あるいは不眠やイライラなど、さまざまな不調が現れます。
つまり、原因のわからない不調の多くは、
脳が「安心できていない」状態にあることから始まっているのです。
心では「大丈夫」と思っていても、
身体や感覚のレベルで脳が“危険信号”を出し続けている。
これこそが「気づかないストレス」の正体であり、
いわば脳の誤警報なのです。
■中高年に多い「体からくるストレス反応」
中高年になると、多くの人が「体の変化」を感じ始めます。
視力が落ちる、聴こえづらくなる、体が硬くなる、反応が鈍くなる。
これらは加齢による自然な変化でもありますが、
実はこの“感覚の変化”が脳にとっては大きなストレス要因になることがあります。
たとえば、目のピントが合いづらくなると、
脳は常に“見よう”と余計な力を使い続けます。
耳の聞こえが悪くなると、
周囲の音情報を拾うために神経を過敏に働かせようとします。
また、関節の可動域が狭くなったり、身体が硬くなったりすると、
脳は「その動きをするのは危険だ」と判断し、
痛みを感じたり、筋肉をさらに固めてしまうこともあります。
つまり、体の変化を脳が「危険」と感じている状態が、
無意識のうちにストレス反応を引き起こしているのです。
それが長く続くことで、
「常に緊張しているような疲れ」「動くと痛む」「リラックスできない」といった慢性的な不調につながっていきます。
■「ストレス=心」という誤解を超えて
多くの方が、「ストレスは心の問題」「気の持ちよう」と考えがちですが、
実際には脳が身体の情報をどう受け取っているかが鍵を握っています。
体の感覚入力がスムーズで、脳が安心できる状態であれば、
人は自然とリラックスでき、エネルギーも安定します。
逆に、感覚情報が乱れていると、脳は常に「緊急モード」で働き続けるため、
どんなに休んでも疲れが取れない、ということが起こります。
つまり、「見えないストレス」とは、
心ではなく脳と身体のコミュニケーションの乱れなのです。
■“気づく”ことが回復の第一歩
中高年の不調は、年齢や生活習慣だけが原因ではありません。
実は、「自分の身体の状態に気づけていないこと」こそが、
慢性的なストレスと不調を生む根本的な要因になっています。
見えにくさ、聴こえにくさ、体の硬さ、姿勢の乱れ。
こうした感覚の変化に“気づくこと”ができれば、
脳はもう一度「安心して動ける身体」を取り戻すことができます。
不調は、身体があなたに送っているメッセージです。
それを無理に押し込めるのではなく、
「なぜ今、脳が不安を感じているのか?」という視点で見つめ直すことが、
本当の意味での“ストレスケア”につながっていきます。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?自覚できるストレスと、自覚できないストレス
「ストレスが溜まっている」と感じるとき、私たちは多くの場合、「仕事が忙しい」「人間関係がうまくいかない」「将来への不安がある」といった、明確に自覚できるストレスを思い浮かべます。
確かにこうした心理的・社会的ストレスは、中高年の不調の大きな原因のひとつです。
しかし実際には、それらをうまくコントロールしている人でも、肩こりや腰痛、頭痛、めまい、倦怠感などの“なんとなく不調”を抱えているケースが少なくありません。
このとき関係しているのが、「自覚できないストレス」です。
自覚できないストレスとは、心ではなく「身体」から生じているストレスのことです。
たとえば、長時間パソコンやスマートフォンを見続けて目の動きが固まっていたり、耳が聞こえにくく周囲の音を拾うのに無意識のうちにエネルギーを使っていたり、足首や股関節が硬くなってバランスを取るために常に緊張していたり。
こうした小さな「身体的な負荷」は、本人が気づかないうちに脳へ“危険信号”として送られ続け、結果として慢性的な緊張や痛み、不安感となって現れるのです。
つまり、不調の原因は「ストレスを感じているから身体がこる」のではなく、「身体が常にこわばっているから脳がストレスを感じてしまう」こともあるのです。
この順序の逆転に気づけるかどうかが、中高年以降の健康を大きく左右します。
■ 見えないストレスの正体は「脳の過剰警戒」
人の脳は、生きるために常に「安全か・危険か」を判断しています。
たとえば、視覚・聴覚・前庭(平衡感覚)などの情報が正しく統合されていれば、脳は「今の状態は安全」と判断し、身体をリラックスさせます。
しかし、視覚がぼやけたり、耳が聞こえづらかったり、身体のバランスが崩れたりすると、脳は正確に状況を把握できません。
その結果、「もしかしたら危険かもしれない」と誤警報を出し、交感神経を優位にして筋肉を緊張させたり、呼吸を浅くしたりするのです。
中高年に多い慢性疲労や倦怠感、肩こり、腰痛、めまい、集中力低下といった症状は、こうした“脳の過剰警戒モード”が背景にあります。
本人は「特にストレスは感じていないのに、なんだか疲れる」「寝てもスッキリしない」と訴えますが、それは心理的ストレスではなく、感覚情報のズレによって起こる身体的ストレスの可能性が高いのです。
■ 「見えていない・聞こえていない・感じていない」が脳を疲れさせる
特に現代社会では、視覚と聴覚の負担が大きくなっています。
スマートフォンの画面を長時間見つめ、平面的な視覚情報ばかりを処理していると、目の筋肉が動かなくなり、視野も狭くなります。
また、イヤホンで常に音を聞いていると、耳の筋肉や内耳の機能が低下し、周囲の環境音とのズレが生じます。
このように感覚器の動きが偏ると、脳は正確な空間認知ができず、わずかな揺れや動きでも不安定に感じるようになります。
それが結果的に「なんとなく落ち着かない」「集中できない」「疲れやすい」という“見えないストレス”に変わっていくのです。
また、関節の硬さや姿勢の崩れも、同様に脳へのストレス信号になります。
たとえば、股関節や足首の可動域が狭くなると、立っているだけでもバランスを取るために多くの筋肉を無意識に使います。
このように「何もしていないのに疲れる」「座っているだけで腰が痛くなる」というのは、身体が常に緊張している証拠です。
その緊張を脳は“ストレス状態”と認識してしまうため、慢性的な不調を引き起こすのです。
■ 中高年に多い「我慢型ストレス反応」
中高年の方ほど、この“自覚できないストレス”に気づきにくい傾向があります。
なぜなら、長年の生活習慣や仕事の責任感から、「多少の疲れは当たり前」「痛いけど我慢できる」といった感覚が染みついているからです。
実際、ある調査では40代以上の男性の約6割が「軽い痛みや不調は放置している」と回答しています。
しかし、その「我慢」が脳の誤警報を慢性化させ、やがてはうつ症状や自律神経の乱れにまで発展することもあります。
つまり、中高年の不調の原因は、「強いストレスを受けているから不調になる」だけでなく、「気づかないストレスを溜め続けているから抜け出せなくなる」という二重構造にあります。
■ “感じ直すこと”が回復の第一歩
このような無意識ストレスを和らげるには、まず「自分の身体の状態を正確に感じ取る力」を取り戻すことが大切です。
たとえば、目の動きをゆっくりと確かめたり、耳から入る音を意識的に聞き分けたり、関節の可動域を確かめたりするだけでも、脳のセンサーは少しずつ再調整されていきます。
また、呼吸の深さやリズムを観察することも効果的です。
これらの行為は単なるリラクゼーションではなく、「今、自分の身体がどう感じているか」を再認識する行為です。
その積み重ねが、脳に「安全である」と伝えるサインとなり、緊張をほどいていくのです。
中高年が抱える不調の原因は、決して“気の持ちよう”だけではありません。
「感じないふりをしてきたストレス」「気づけなかった身体のSOS」が、静かに脳を疲弊させているのです。
だからこそ、「見えるストレス」だけでなく、「見えないストレス」にも目を向けていくことが、これからの健康づくりにおいて欠かせない視点だと言えるでしょう。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?脳は「体のセンサー情報」で安心・不安を判断している
脳は「体のセンサー情報」で安心・不安を判断している
私たちは「ストレスを感じる」と聞くと、心の中で起きている感情的な反応をイメージしがちです。
しかし実際のところ、ストレスの感じ方を決めているのは脳であり、そして脳は「体のセンサー情報」によって安心・不安を判断しています。
つまり、私たちがリラックスできるかどうか、逆に緊張や不調を感じるかどうかは、「身体の状態が脳にどう伝わっているか」で大きく変わるのです。
■ 脳は常に「今、安全か?」をモニタリングしている
脳は一瞬たりとも休むことなく、体のあらゆるセンサーから送られる情報をもとに「いま自分は安全か危険か」を判断しています。
そのセンサーとは、視覚、聴覚、平衡感覚(前庭)、筋肉や関節の感覚(固有感覚)、そして皮膚の触覚などです。
これらの情報がスムーズに統合されていれば、脳は「自分の身体は安定している」「周囲の状況も予測できる」と認識し、安心状態=副交感神経優位なリラックスモードを維持します。
ところが、これらのセンサーのどこかが鈍くなったり、偏って働いたりすると、脳は正確に現状を把握できなくなります。
その結果、危険がないにもかかわらず「何かおかしい」「もしかしたら危険かもしれない」と判断して、交感神経を活性化させてしまうのです。
これがいわゆる脳の誤警報であり、慢性的な緊張や疲労、痛み、めまい、イライラなどの“中高年の不調”の原因になることが多く見られます。
■ 不調のサインは「センサーのズレ」から生まれる
たとえば、視覚のセンサー。
中高年になると老眼やピント調節機能の低下が進みます。
ピントが合いづらい状態で長時間作業をすると、眼の筋肉だけでなく、首や肩の筋肉まで無意識に緊張します。
脳は「視界が安定しない=バランスが崩れている」と判断し、体幹を固めてバランスを取ろうとするため、肩こりや頭痛といった不調が生まれるのです。
聴覚のセンサーも同じです。
耳が聞こえづらくなると、脳は「環境の把握が難しい」と感じ、外の音を拾うために常に集中状態になります。
その結果、脳の覚醒レベルが下がらず、睡眠の質が低下したり、日中に疲れやすくなったりします。
このように、ストレスの原因が“耳の疲労”にあるとは思わず、「最近ストレスが多いせいかな」と心理的な理由にすり替えてしまうケースが多いのです。
また、関節や筋肉のセンサー(固有感覚)の低下も中高年の不調に大きく関わっています。
体のどこかが硬くなったり、動きの感覚が鈍ったりすると、脳は「姿勢が不安定」と判断します。
その不安定さを補おうとして、身体の他の部位に余計な力が入り、結果的に慢性的な緊張を生み出します。
これが、いわゆる「原因不明の肩こり」や「どこに行っても良くならない腰痛」の背景にある“センサーのズレ”です。
■ ストレスの感じ方は「体の状態」が決めている
つまり、「ストレスを感じる」とは、単に気持ちの問題ではなく、脳が受け取る身体情報に大きく依存しています。
たとえば、脳に入ってくる情報のうち、実に約80〜90%が身体からの入力だといわれています。
これはつまり、「脳は身体の状態をもとに世界を解釈している」ということです。
たとえば、身体が緊張して呼吸が浅い状態では、脳は「危険が近い」と感じやすくなります。
逆に、身体がリラックスして呼吸が深いときは、脳は「安全だ」と判断しやすく、同じ出来事に対してもストレスを感じにくくなります。
つまり、心が身体に影響を与えるのと同じように、身体のセンサー情報が心の状態をつくっているのです。
このメカニズムは中高年の不調において特に重要です。
年齢とともに筋肉や関節の柔軟性、視覚や聴覚の鋭さが低下し、身体からのセンサー情報の質が下がることで、脳が「不安定だ」と誤認しやすくなります。
それが「原因のはっきりしないストレス」や「自律神経の乱れ」として現れてくるのです。
■ 「見直すべきは心よりも、まず身体のセンサー」
「ストレスを減らす」と聞くと、心を整える、考え方を変える、環境を改善するといった方法を思い浮かべる人が多いかもしれません。
もちろんそれらも大切ですが、脳が安心を感じられるためには、まず「身体からのセンサー情報を整える」ことが欠かせません。
たとえば、
・目をゆっくりと上下左右に動かして、眼球の動きを感じる
・耳を軽くマッサージして、周囲の音を意識的に聞き分ける
・足首や股関節をゆっくり動かして、バランス感覚を確認する
・呼吸の深さや速さを感じ取り、意識的にゆるめていく
こうしたシンプルな動作でも、脳に「今は安全だ」という情報を送り戻すことができます。
この安全信号が積み重なることで、交感神経の緊張が和らぎ、心のストレス反応も自然と落ち着いていくのです。
■ 不調の原因は「脳の誤解」かもしれない
中高年の方の中には、「最近ストレスを感じやすくなった」「小さなことでイライラする」「体がいつも重い」と感じている方が多くいます。
けれどもその原因は、性格や精神的な弱さではありません。
むしろ、身体からのセンサー情報が正しく脳に届かず、「不安定=危険」と誤解しているだけかもしれません。
つまり、不調とは脳の誤解、あるいは誤警報なのです。
安心を感じる力は、心だけでなく、身体のセンサーを整えることで取り戻すことができます。
そのために大切なのは、我慢ではなく「感じること」。
自分の身体がどう動き、どう感じているのかを少しずつ意識するだけでも、脳は新しい情報を受け取り、「安心」を再学習していくのです。
中高年にとって、健康を守るうえで本当に大切なのは、「ストレスを減らすこと」ではなく、「脳が安心できる身体の状態をつくること」です。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?感覚の乱れが脳を疲弊させる — 眼・関節・耳の隠れストレス
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?「眼の見えにくさ」が引き起こす無意識のストレス
中高年の不調の原因を探るとき、多くの方は「運動不足」「睡眠の質」「食生活」「仕事や人間関係のストレス」といった項目を思い浮かべます。
しかし、実際に身体や心の状態を左右しているのは、それらよりももっと身近な「感覚器官の疲労」であることが少なくありません。
その中でも特に見落とされやすいのが、「眼の見えにくさ」による無意識のストレスです。
■ 見えづらさは「脳への負担」だった
私たちは日常生活の約8割以上の情報を視覚から得ています。
つまり、眼の状態はそのまま脳の働きに直結しています。
たとえば、ピントが合いづらい、文字がかすむ、暗い場所で見えにくい、こうした「見えにくさ」は、眼のトラブルのようでいて、実は脳にとって大きなストレス要因なのです。
視覚は単に“ものを見る”機能ではなく、「空間の把握」「動きの予測」「バランスの維持」といった生命活動の基盤を担っています。
眼がうまく焦点を合わせられない状態では、脳は常に「今、どこにいるのか」「身体がどちらを向いているのか」を正確に認識できません。
その結果、脳は安全確認のために覚醒状態を維持し、交感神経を優位にしてしまいます。
これが、「見えにくさによる無意識のストレス」の正体です。
このストレスは、明確に自覚できるものではありません。
むしろ「視界が少しぼやけているけど問題ない」「疲れ目くらい」と軽く見てしまいがちです。
しかし脳にとっては、ピントを合わせるために常に筋肉を緊張させ、情報を補正するために多くのエネルギーを使う、まさに「慢性ストレス状態」といえます。
その負担が積み重なると、肩こりや首こり、頭痛、集中力低下、イライラ、不眠など、まるで心理的ストレスと同じような症状を引き起こします。
■ 「眼精疲労」ではなく「脳疲労」
眼が疲れていると思ってマッサージや温めをしても、一時的にしか楽にならないという経験はありませんか?
それは、実際に疲れているのが“眼”そのものではなく、“脳”だからです。
眼球の動きは6本の外眼筋によって制御され、それをコントロールしているのが中脳や前頭葉の神経回路です。
つまり、眼が正しく動かないということは、脳の働きが乱れているサインでもあります。
特に中高年になると、近くを見る時間の増加(スマートフォンやパソコン作業)と、遠くを見る機会の減少によって、眼の筋肉が偏った使われ方をします。
この状態が続くと、眼球の動きが固まり、左右の眼がうまく協調できなくなります。
すると、ものを立体的にとらえる力が落ち、距離感や奥行き感がつかみにくくなります。
この「空間認知のズレ」を脳は「不安定」と判断し、身体を固めるように指令を出します。
結果として、姿勢が硬くなり、肩や腰の筋肉が常に緊張し続ける、これが、眼の見えにくさが身体の不調につながる仕組みです。
■ 視覚と自律神経の密接な関係
視覚情報は、脳幹や視床下部といった自律神経の中枢に直結しています。
そのため、視覚の乱れは自律神経のバランスにも影響を与えます。
たとえば、スマートフォンの強い光を長時間浴び続けると、交感神経が刺激され、脳は“昼”と認識し続けます。
その結果、夜になっても副交感神経が優位になれず、寝つきが悪くなったり、浅い眠りが続いたりします。
また、眼が疲れている状態では、まばたきの回数が減り、呼吸が浅くなりやすい傾向があります。
呼吸が浅いと二酸化炭素の排出量が減り、脳血流が悪化します。
この悪循環によって、頭がぼーっとしたり、集中できなかったりする状態が生まれるのです。
「疲れ目がひどい」「パソコンのあとに肩がこる」という訴えの多くは、実はこうした視覚由来の自律神経ストレスが関係しています。
■ 中高年特有の「焦点ストレス」
加齢に伴い、眼のピント調節機能は徐々に低下します。
これは「水晶体」と呼ばれるレンズの弾力が失われ、毛様体筋の働きが鈍くなるためです。
近くが見えづらいとき、人は無意識に眉間に力を入れたり、首を前に突き出したりして焦点を合わせようとします。
この小さな動作が繰り返されることで、首の後ろの筋肉(後頭下筋群)や僧帽筋が緊張し、血流が悪化します。
つまり、中高年に多い「首・肩のこり」や「目の奥の痛み」は、単なる筋肉疲労ではなく、焦点調節を補うための“姿勢ストレス”でもあるのです。
この状態が続くと、脳は常に「体を支えるための緊張」を必要とし、リラックスする時間を失います。
やがて「なんとなく疲れが抜けない」「休日でも気持ちが休まらない」という慢性的な不調へとつながります。
■ 眼を休ませることは、脳を休ませること
「眼を休ませる」と聞くと、目を閉じる、遠くを見る、温めるなどをイメージするかもしれません。
もちろんそれらも効果的ですが、重要なのは「眼の動きを取り戻すこと」です。
たとえば、ゆっくりと上下左右に眼を動かす、まぶたを閉じて円を描くように眼を動かす、といったシンプルな動作だけでも、外眼筋と脳幹の回路が再び活性化します。
また、光の強さを調整するのも大切です。
明るすぎる環境では交感神経が刺激され、暗すぎると逆に集中力が低下します。
自然光に近い穏やかな明るさを意識し、画面との距離を適度に保つことで、眼と脳の緊張が和らぎます。
そして何よりも、「見えにくさを我慢しない」こと。
老眼や視力低下を「年のせい」と片付けず、必要であれば眼鏡やレンズを調整し、見え方を整えることは、脳の安心感を取り戻すうえで極めて重要です。
中高年の不調の原因として、「眼の見えにくさ」は意外にも深く関係しています。
それは、単なる視力の問題ではなく、「脳がどれだけ正確に世界を感じ取れているか」という根本的なテーマに関わるからです。
視覚が安定すれば、脳は安心し、身体は自然にゆるみます。
逆に、視覚が乱れれば、脳は常に不安を感じ、身体は硬直します。
「最近ストレスが多い」「疲れやすい」と感じたとき、もしかするとそれは“眼”から始まる無意識のストレスかもしれません。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?「関節の硬さ」は脳と体の“通信エラー”
中高年になると、「体が硬くなった」「前より動きにくい」「同じ姿勢がつらい」と感じる方が増えてきます。多くの方はそれを「加齢だから仕方ない」と考えがちですが、実はその“関節の硬さ”こそが、脳にストレスを与え、不調を引き起こす大きな原因のひとつになっています。つまり、筋肉や関節の問題と思われがちな不調の背景には、脳と体の“通信エラー”が潜んでいるのです。
■ 関節の硬さが脳に与える見えないストレス
関節は単なる「曲げ伸ばしのためのパーツ」ではなく、実は高性能なセンサーの集合体です。関節の内部には「固有受容器」と呼ばれる神経センサーがあり、姿勢や動きの微妙な変化を常に脳へ報告しています。
このセンサーが送る情報は、脳にとって「自分の体が今どんな状態なのか」を知るための基礎データです。たとえば「肩がどの位置にあるか」「足がどれくらい傾いているか」といった情報をもとに、脳は姿勢を安定させたり、必要に応じて筋肉を動かしたりしています。
ところが中高年になると、長年の姿勢の癖や運動不足、デスクワークなどによって、関節の可動域が狭くなり、固有受容器からの情報が曖昧になります。脳が受け取る体の“位置情報”が不正確になると、脳は「体の状態がわからない」という不安を感じます。この“不確かさ”こそが、脳にとって大きなストレスなのです。
■ 「動かないこと」で強まる誤作動のループ
関節の動きが少なくなると、脳が受け取る感覚情報の量が減ります。感覚が少ないほど、脳は「安全かどうか判断できない」状態に陥ります。すると脳は、“念のため”という形で筋肉を固め、関節を守ろうとします。これが「体のこわばり」や「慢性的な肩こり」「腰の重さ」として現れます。
この反応自体は防衛本能として自然なものですが、問題はその状態が長期化することです。脳が「体は危険な状態かもしれない」と誤解したまま筋肉を固め続けると、さらに関節が動かなくなり、感覚情報がますます減少します。結果として、脳はますます不安を強め、筋肉を固めるという悪循環が起こるのです。
この“通信エラーのループ”は、本人が自覚しづらく、長年かけてじわじわと蓄積します。そのため、突然「ぎっくり腰」や「寝違え」といった形で、ある日限界が爆発することも少なくありません。
■ 関節の硬さは「危険信号」ではなく「感覚の鈍り」
中高年の不調を単なる「硬さ」「老化」と片づけてしまうと、本当の原因を見逃してしまいます。多くの場合、関節が硬くなっているのは「柔軟性が足りない」からではなく、「脳が安心できるだけの感覚情報が届いていない」からです。
つまり、関節の硬さは「危険信号」ではなく、「脳が体を信頼できていない」というサインなのです。
たとえば、長年デスクワークを続けている方の多くは、股関節や肩甲骨が動かなくなり、腰や肩に慢性的な不調を感じています。これは単に筋肉が硬いわけではなく、脳が「その関節を動かすことが危険」と誤認している状態。脳がその部分の感覚をうまく処理できないため、動かすことを“制限”しているのです。
このような誤認が続くと、脳は体のマッピング(身体地図)を正確に描けなくなり、姿勢バランスや歩行にも影響を及ぼします。実際、「片足で立てない」「歩くとふらつく」「階段が怖い」といった中高年の不調も、この“感覚地図の乱れ”が原因になっていることが多いのです。
■ 脳に「安心」を取り戻す関節の使い方
関節の硬さを改善するために、ただストレッチをすればよいというわけではありません。大切なのは、「脳に正しい情報を再教育する」ことです。
たとえば、ゆっくりとした動きで関節の角度を確かめながら動かす、動かしている部位に意識を向ける、深呼吸をしながら関節の動きを感じ取る、こうした“感覚に気づく運動”は、固有受容器を目覚めさせ、脳と体の通信を回復させます。
関節を滑らかに動かすことは、単に筋肉を柔らかくするだけでなく、脳に安心感を与える作業です。脳が「この体は安全に動ける」と認識すれば、筋肉の過緊張が解け、動きやすさが自然に戻っていきます。これは物理的なトレーニングというよりも、「感覚の再接続」なのです。
■ “柔軟性”よりも“つながり”を整える
中高年の不調の多くは、「筋力の低下」や「関節の老化」といった構造的な問題に見えますが、根底には「脳と体のつながりの低下」という機能的な問題があります。
ですから、ストレッチやマッサージだけでなく、「脳が体を再び信頼できる状態」を取り戻すことが、不調解消の鍵になります。たとえば、関節を大きく動かすよりも、小さな角度で“痛くない範囲”を繰り返し動かす方が、脳に安心感を与えやすいケースもあります。
柔軟性を高めることはもちろん大切ですが、それ以上に大切なのは、脳が「自分の体を正しく感じ取れる状態」を作ること。
関節がしなやかに動くということは、脳と体の信頼関係が回復した証でもあります。これが中高年における「真の柔軟性」なのです。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?「聴覚の鈍り」が自律神経を乱す
中高年になると、「最近、人の声が聞き取りづらい」「テレビの音量を少し大きくしないと聞こえない」と感じる方が増えてきます。こうした聴覚の変化は加齢による自然なものと思われがちですが、実はこの“聴覚の鈍り”が、脳と自律神経に見えないストレスを与え、全身の不調の原因となっていることが少なくありません。
■ 聴覚は「安全センサー」として働いている
人間の聴覚は、単に音を聞くだけの機能ではありません。脳は常に周囲の音を分析し、環境の安全を判断しています。たとえば、後ろから車が近づく音、ドアの開閉音、人の話し声など、私たちは意識していなくても、聴覚を通じて「今、安心していていいのか」を脳が評価しています。
つまり、聴覚は「安全センサー」のような役割を果たしており、脳が安心して活動するために欠かせない感覚なのです。
ところが、中高年になると耳の感度が下がり、音の一部が聞き取りづらくなります。そうすると、脳は「情報が欠けている」と判断し、環境の安全を確信できなくなります。
この“不確かさ”が、脳にとってストレスになります。
■ 「聞き取れないこと」がもたらす無意識の緊張
たとえば、会話中に相手の言葉が聞き取りづらいとき、私たちは無意識に集中力を高め、顔を近づけ、眉をひそめ、姿勢を前のめりにして聞こうとします。
このとき脳は「情報を聞き漏らすまい」と緊張し、身体の筋肉や交感神経も同時に緊張状態になります。
つまり、「聞き取りづらさ」は、本人が意識しないうちに交感神経を優位にするトリガーになっているのです。
このような状態が日常的に続くと、脳は常に軽い“戦闘モード”のような状態に置かれます。眠りが浅くなったり、肩や首がこわばったり、動悸や息苦しさを感じることもあります。本人は「特にストレスは感じていない」と思っていても、実際には「聞こえにくさ」という感覚ストレスが、自律神経を通して体に負担をかけているのです。
■ 「脳が聞いている」という事実
耳で音を受け取るのは聴覚の入り口に過ぎません。実際に“聞く”という作業をしているのは、耳ではなく脳です。
音は外耳から鼓膜、耳小骨、内耳の蝸牛を経て電気信号に変換され、聴覚野へ送られます。そこで脳が「これは人の声」「これは車の音」と識別しています。
つまり、聴覚の処理には膨大なエネルギーが使われています。音が不明瞭になったり、一部の周波数が聞き取りづらくなったりすると、脳はそれを補うために余計なエネルギーを消費します。
これが、「聞こえにくさ」が脳を疲弊させる仕組みです。
脳が常にフル稼働している状態では、副交感神経がうまく働けず、リラックスしづらくなります。これが長期化すると、頭痛やめまい、集中力低下、慢性的な疲労感など、いわゆる中高年特有の「なんとなく不調」につながっていくのです。
■ 「静かすぎる環境」が脳に与える影響
一見すると「静かな環境」はリラックスできるように思えますが、実は聴覚的な刺激が少なすぎることも、脳にストレスを与えることがあります。
人の脳は「音の変化」を通じて周囲を把握しています。一定の生活音や自然音が聞こえることで、「今は安全な環境にいる」と認識できるのです。
しかし、聴覚が鈍ってくると、脳が受け取る音情報が減り、環境の変化を正しく把握できなくなります。脳は“静かすぎる”状況を「何かおかしい」と判断し、軽い警戒モードに入ります。
この警戒状態は、自律神経のバランスを乱し、無意識の緊張感を生み出します。つまり、耳の感度が低下するだけで、脳は「常に周囲を確認しているような疲れた状態」になってしまうのです。
■ 「音の方向」がわからない不安
中高年になると、聴覚の鈍りに加えて、音の方向感覚が曖昧になる方も増えます。
左右の耳の聞こえ方に差があると、音源の位置を正確に特定できなくなり、脳は空間の把握に苦労します。これもまた、自律神経の緊張を引き起こす要因になります。
たとえば、誰かに後ろから話しかけられたときに「どこから声がしたのか」すぐにわからないと、一瞬体がビクッと反応します。この「ビクッ」という反応は、交感神経の急な興奮によって起こるものです。
つまり、聴覚情報の不正確さは、脳にとって“常に驚かされている状態”を作り出します。こうした反応が積み重なると、慢性的な肩こり、頭の重さ、集中力の低下などにつながるのです。
■ 聴覚と姿勢・バランスの関係
耳には聴覚だけでなく、平衡感覚を司る「前庭系」もあります。
音の感度が低下すると、前庭系への刺激も少なくなり、姿勢バランスに影響を及ぼすことがあります。中高年でよく見られる「フラつき」「まっすぐ歩きにくい」「片足立ちが不安定」といった症状も、実は聴覚の衰えが関係している場合があります。
聴覚と前庭系は密接に連動しており、耳から入る情報が少なくなることで、脳は「自分がどこにいるのか」を感じ取りにくくなります。これもまた、自律神経にとって大きなストレスとなり、身体の緊張や疲労感として現れます。
■ 聴覚を整えることは「脳を休ませること」
聴覚の鈍りを感じたときに大切なのは、単に「聞こえを改善する」ことではなく、「脳が安心できる聴覚環境を整えること」です。
たとえば、自然音(川のせせらぎや風の音など)を日常に取り入れたり、音楽を“聞く”よりも“感じる”ように楽しむことも有効です。
また、左右の耳に均等に音を入れるよう意識したり、静かな環境にこもりすぎず、適度な音の刺激を受けることも、脳の安心感を保つ助けになります。
さらに、耳のストレッチや軽いマッサージで血流を促すことも、聴覚器官の働きをサポートします。耳介を優しく引っ張ったり、周囲を温めることで、内耳への血流が改善され、感覚の鈍りを和らげる効果が期待できます。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?整えることで蘇る脳の安心 — 不調を味方に変える生き方
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?身体の“誤作動”が続くと、慢性的な不調へ
身体の“誤作動”が続くと、慢性的な不調へ
中高年になると、「なんとなく体が重い」「寝ても疲れが取れない」「常にどこかが痛い」といった漠然とした不調を抱える方が増えていきます。
しかし、検査をしても明確な異常が見つからず、「年のせい」「自律神経の乱れ」と片づけられてしまうことも少なくありません。
実は、この“説明のつかない不調”の多くは、脳が誤った危険信号を出し続けている状態=身体の“誤作動”によって引き起こされています。
そして、この誤作動が慢性化すると、身体は常に防衛モードのままになり、結果として不調が“クセ”のように定着してしまいます。
■ 脳が出す“誤作動信号”とは?
私たちの脳は、体のあらゆるセンサー(視覚、聴覚、筋肉や関節の感覚など)から情報を集め、今の状態が「安全」か「危険」かを判断しています。
この仕組みは本来、私たちを守るためのものです。たとえばケガをしたとき、脳は痛みを出して動きを制限し、回復を促します。
しかし、脳が間違った情報を受け取ると、実際には危険でないのに“危険信号”を出し続けることがあります。これが、いわゆる“誤作動”です。
中高年になると、この誤作動が起こりやすくなります。
長年の姿勢の癖、感覚の鈍り、ストレスや睡眠不足などにより、脳が受け取る身体情報が歪んでしまうからです。
結果として、脳は常に「どこかが危ない」「体が整っていない」と誤認し、筋肉を固めたり、交感神経を優位にしたりして防衛モードを続けてしまいます。
■ 防衛モードが続くと何が起こるのか
脳が体を守ろうとしている間、実際には“守るための緊張”が全身に広がります。
この状態が短期間なら問題ありませんが、長期化すると、脳と自律神経のバランスが崩れ、さまざまな慢性不調へとつながっていきます。
たとえば、
・肩こりや腰痛がずっと取れない
・呼吸が浅くなり、疲れやすい
・睡眠の質が悪く、朝起きてもスッキリしない
・集中力が続かない
・常にどこかが重だるい
こうした症状は、筋肉や関節の問題だけではなく、脳が「まだ危険が去っていない」と感じているサインです。
防衛反応が“解除されない”ため、身体がリラックスできず、回復のスイッチが入らなくなっているのです。
■ 「不調のクセ」ができるメカニズム
身体の誤作動が続くと、脳はその状態を“新しい通常”として記憶します。
たとえば、慢性的に肩がこっている人の脳は、「肩の筋肉が常に緊張している状態」を安全だと誤認するようになります。
すると、少しでも姿勢を変えたり、力を抜こうとしたりしても、脳が「それは危険だ」と判断して再び筋肉を固めてしまうのです。
このようにして、“不調のクセ”が脳に書き込まれます。
脳は変化を嫌うため、一度覚えたパターンを維持しようとします。
結果として、筋肉・神経・内臓までもが誤作動の影響を受け、慢性的な疲労や痛み、血流の低下、消化不良など、広範囲な不調が起こっていきます。
■ 自覚できないストレスが誤作動を強化する
ここで重要なのは、この“誤作動のループ”を強化しているのが、心で感じるストレスだけではないということです。
中高年の不調の多くは、仕事や人間関係などの心理的ストレスよりも、「身体からくるストレス」によって脳が疲弊しているケースが非常に多いのです。
たとえば、視覚情報がぼやける、耳が聞こえづらい、関節が硬いといった小さな感覚の乱れも、脳にとっては「情報が欠けている」というストレスになります。
脳は“体の状態がわからない”ことを危険と判断し、防衛モードを強化します。これが、誤作動をさらに固定化させる要因になります。
つまり、不調の原因は「ストレスがあるから体が硬くなる」のではなく、「感覚が乱れていることで脳がストレスを感じている」という逆転した構造なのです。
■ 「治そうとするほど悪化する」理由
中高年の方が陥りやすいのが、「治そうと頑張るほど症状が悪化する」というパターンです。
たとえば、肩こりを解消しようと強くマッサージしたり、痛みを我慢してストレッチを続けたりすると、一時的に筋肉はほぐれたように感じます。
しかし、脳がまだ「そこは危険」と判断している状態では、体がすぐに元の緊張に戻ってしまいます。
このとき脳は、「思うように動けない=まだ危険だ」と誤認し、余計に筋肉を固めて防衛します。
つまり、脳が安心していない状態では、どんなに体を整えても一時的な改善にしかならないのです。
これが、誤作動が慢性化する最大の原因といえるでしょう。
■ 誤作動を解く鍵は「脳に安心を教えること」
慢性的な不調を改善するためには、まず脳に「もう危険ではない」と伝えることが大切です。
そのためには、“無理をしない穏やかな刺激”を積み重ねていくことが効果的です。
たとえば、深い呼吸を意識したり、痛みを感じない範囲で体を動かしたり、目や耳、関節などの感覚を丁寧に感じ取ることです。
これらの動きは、脳に「今は安全だ」という情報を少しずつ届けます。
脳が安心を取り戻すことで、防衛モードが解除され、体の緊張や痛みが自然にほどけていきます。
つまり、不調を「敵」として排除するのではなく、「脳が安心を失っているサイン」として受け止めることが、回復の第一歩なのです。
■ 不調は「脳からのSOS」
中高年の不調は、単なる老化や体力低下ではなく、脳が安心を失っていることを知らせるSOSでもあります。
体のどこかが痛む、重い、動きづらい――それは、「感覚の誤作動が起きているよ」という脳からのメッセージです。
不調を無理に消そうとせず、体が発する小さなサインに耳を傾けることで、誤作動の原因に気づくことができます。
この気づきがあるだけで、脳の緊張は少しずつ解けていきます。
なぜなら、脳は「自分の状態を理解できている」と感じるだけで安心するからです。
それが、慢性的な不調を根本から癒す第一歩になるのです。
まとめると、中高年に多く見られる慢性的な不調の原因は、脳が誤った危険信号を出し続けている“誤作動”にあります。
この誤作動が続くと、体は常に防衛モードのままになり、筋肉の緊張、血流の低下、自律神経の乱れといった悪循環が起こります。
しかし、これは決して治らない状態ではありません。
脳に「安心」を取り戻させることで、誤作動は自然に解け、体は再び本来のバランスを取り戻していきます。
不調は、脳が発している“まだ整っていないよ”というメッセージです。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?自分でできる“感覚チェック”とリセット法
中高年になると、若いころには感じなかった「なんとなくの不調」を抱える方が増えます。
疲れが抜けない、気力が湧かない、体が重い、眠りが浅い。
これらの不調の原因の一つは、身体の感覚のズレにあります。
つまり、脳が「今の身体の状態」を正確に把握できなくなっているのです。
この“感覚のズレ”は、目や耳、筋肉、関節など、体のセンサーから入る情報が歪んでいることが原因で起こります。
そして、この状態が続くと、脳は常にストレスを感じ、体を緊張させたり、交感神経を優位にしたりしてしまいます。
その結果、「休んでも回復しない」「気持ちは元気なのに体が動かない」といった中高年特有の慢性的な不調につながるのです。
しかし、感覚のズレは“自分で気づく”ことができます。
そして、“脳を安心させるリセット”を行うことで、少しずつ整えていくことが可能です。
ここでは、誰でも簡単にできるセルフチェックとリセット法をご紹介します。
■ 1. 「今の自分の状態」を観察する感覚チェック
まず大切なのは、今の自分の身体を感じ取ることです。
中高年の方の多くは、長年の生活習慣やストレスによって「感覚の鈍さ」が蓄積しています。
この感覚の鈍さが、脳に誤った情報を送り、不調の原因となるため、まずは“自分を知る”ことから始めます。
チェック① 重心の位置
目を閉じて立ち、足裏のどこに重さを感じるかを観察します。
つま先側・かかと側・左右のどちらかに偏っていませんか?
もし偏りを感じるなら、脳が身体のバランス情報を正確に受け取れていない可能性があります。
これも一種の“感覚ストレス”です。
チェック② 呼吸の深さ
深呼吸をしてみて、胸とお腹のどちらが動くかを意識してみます。
胸だけが動いている場合、呼吸が浅くなっており、自律神経が緊張モードに傾いているサインです。
これは脳が「安全ではない」と感じている状態でもあります。
チェック③ 視界の安定感
まっすぐ前を見たとき、視界がクリアで安定していますか?
あるいは、焦点が合いにくい、目がすぐ疲れるなどの感覚はありませんか?
視覚情報の乱れも、脳にとってはストレスであり、不調の大きな原因になります。
チェック④ 身体の左右差
軽く首を回したり、肩をすくめたり、前屈してみてください。
左右で動かしやすさや違和感があるなら、それも脳が“片側の情報をうまく処理できていない”サインです。
痛みがあるわけではなくても、感覚の非対称はストレスとして蓄積していきます。
■ 2. チェック後の「リセット」は“安心を取り戻す時間”
チェックによって今の状態を知ったあとは、“改善しよう”と頑張るのではなく、脳に安心を感じさせるリセットを行います。
リセットとは、力を抜き、身体が「もう守らなくていい」と判断できる状態をつくることです。
中高年の方ほど、この「安心の再学習」が回復の鍵になります。
リセット法① 呼吸のリズムを整える
深呼吸ではなく、“ゆっくり吐く”ことを意識します。
吐く息を長くすることで、副交感神経が優位になり、脳が安全信号を受け取ります。
「フーッ」と口から静かに息を吐きながら、肩や背中の緊張が抜けていく感覚を味わってください。
リセット法② 触覚による安心づくり
手のひらで自分の腕やお腹を軽くさすります。
これは、皮膚を通じて脳に「自分の身体を感じている」という安心情報を送る行為です。
力を入れず、ゆっくり、温かさを感じながら行うのがポイントです。
感覚が戻ることで、体と心がつながり、脳の緊張がゆるみます。
リセット法③ 視覚のリセット
目を閉じ、数秒間、遠くを見るような意識を持ちます。
その後、ゆっくり目を開けて周囲を見渡しましょう。
焦点を一点に固定せず、「広がり」を感じるように視野を保ちます。
視覚の過緊張が緩むと、脳への情報処理が穏やかになり、頭の重さや目の疲れが軽くなっていきます。
リセット法④ 微細な動きを感じる
大きく動かす必要はありません。
指先をゆっくり曲げ伸ばししたり、首をわずかに回したりしながら、「どんな感覚があるか」を丁寧に感じてください。
このとき、「もっと動かそう」と頑張る必要はありません。
むしろ、動かすことで感じる“わずかな変化”を脳がキャッチすることで、誤作動のリセットが始まります。
■ 3. 感覚リセットがもたらす「脳の安心」
感覚のズレを修正し、脳に安心を取り戻すことで、
・筋肉の過緊張が自然に緩む
・呼吸が深くなり、睡眠の質が上がる
・消化機能や血流が改善する
・気持ちが落ち着き、イライラが減る
といった変化が現れます。
これは、単なるリラックスではなく、脳が「今は安全だ」と再認識するプロセスです。
つまり、脳の誤作動が解けることで、不調の根本原因であるストレスループが断ち切られるのです。
中高年の不調は、体力の衰えよりも、「脳が安心を忘れていること」から生まれている場合が多いものです。
ですから、日々の小さなセルフケアこそが、最も効果的なストレスケアでもあります。
■ 4. 日常に取り入れるための工夫
感覚チェックとリセットは、1回数分で十分です。
たとえば、
・朝起きたときに重心を確認する
・デスクワークの合間に呼吸を整える
・夜寝る前に腕を軽くさする
といった形で、生活の中に自然に取り入れることが大切です。
ポイントは、「頑張らないこと」と「比べないこと」。
“昨日より楽に動けた”という小さな実感を積み重ねることで、脳は次第に安心を思い出していきます。
その積み重ねが、不調を味方に変える最大の近道です。
中高年に多い慢性的な不調の原因は、脳が身体の感覚を正確に把握できず、ストレスを感じ続けていることにあります。
しかし、感覚を観察し、安心を取り戻すリセットを行うことで、脳は再び安全を感じ取ることができます。
不調は「壊れたサイン」ではなく、「整えるきっかけ」です。
自分の身体を観察し、穏やかにリセットを重ねることで、
中高年の心と身体は本来の回復力を取り戻していきます。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?不調を「敵」とせず、“気づく力”を取り戻す
ここまでのお話を全部まとめると、私たち中高年が感じている「なんとなく調子が悪い」という不調の多くは、実は“気づかないストレス”が関係しているということになります。
ストレスというと、仕事や人間関係などの「心の負担」を思い浮かべがちですが、実際にはもっと静かで目に見えないストレスが、身体の奥でじわじわと積み重なっています。
それが、眼の見えにくさ、関節の硬さ、耳の聞こえにくさなど、感覚の乱れから生まれる「身体由来のストレス」です。
脳は、私たちの身体のセンサー(視覚・聴覚・触覚・関節感覚など)から送られてくる情報をもとに、「安心していいのか」「危険なのか」を判断しています。
ところが、このセンサーがうまく働かなくなると、脳は“誤った信号”を受け取り、実際には安全なのに「不安定だ」「危険だ」と勘違いしてしまいます。
この“誤警報”こそが、肩こりや腰痛、疲労感、集中力の低下など、さまざまな不調を引き起こす原因となっています。
たとえば、眼が疲れてピントが合いづらくなると、脳は常に情報を補正しようとしてフル稼働し、知らないうちにエネルギーを消耗します。
関節が硬く動きづらくなると、身体の位置情報が曖昧になり、脳は「バランスを取るため」に筋肉を過剰に緊張させてしまいます。
また、耳の聞こえが鈍くなると、音を聞き取るために余分な集中を要し、脳が慢性的に疲弊します。
こうした小さなズレが積み重なると、自律神経のバランスが崩れ、「慢性的な不調」として現れてきます。
つまり、不調は“敵”ではなく、身体が「ちょっと助けて」と伝えてくれているサイン。
無理に我慢したり、「気のせいだ」と片付けてしまうのではなく、気づくことこそが回復の第一歩になります。
そして、その「気づく力」を取り戻すためには、自分の感覚をチェックして、整えていくことが大切です。
たとえば、片目ずつ遠くと近くを見比べてみたり、首や肩の動きやすさを左右で比べてみたり、静かな場所で左右の耳の聞こえ方を確かめてみたり。
そんな小さな習慣を通して、自分の身体がいまどんな状態にあるのかを知ることができます。
そのうえで、深呼吸や軽いストレッチ、温めるケアなど、身体が安心できる環境を整えていくことが、脳をリセットする一番の近道になります。
中高年の不調は、決して「老化」だけが原因ではありません。
身体のセンサーと脳とのつながりを少し整えるだけで、驚くほど軽やかに回復していくことが多いのです。
ストレス社会のなかで大切なのは、「ストレスをなくすこと」ではなく、「自分のストレスに気づける状態を保つこと」。
それができるようになると、脳も身体も安心し、本来のリズムを取り戻していきます。
これまでのお話を通してお伝えしたいのは、
“健康とは、頑張ることではなく、感じること”ということです。
「今日は少し疲れているな」
「最近、目がしょぼしょぼする」
「なんだか音がこもって聞こえる」
そんな小さな違和感を無視せず、「よし、ちょっと整えてみよう」と思える心の余裕こそが、真の健康への第一歩です。
不調は、身体があなたに送っている“メッセージ”です。
その声を聞けるようになれば、不調はやがてあなたの味方になってくれます。
そして、その瞬間から、ストレスに振り回される生き方から、“自分の感覚とともに生きる生き方”へと変わっていくことにつながります。
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?まとめ
いかがでしたでしょうか?
重要性を印象付けるため、重複する内容を語る部分も多くありましたが、それだけ五感の感覚と健康は密接に結びついています。
今まで目や耳が腰痛や肩こり、痛みの原因になっているなんてきっと思ったことある人は少ないですよね?(笑)
だからこそ、中高年の方々には気づいて頂きたいですし、こういった仕組みで不調が出ていることを知って頂きたいと思います。
こちらの記事をお読みいただいて、ご興味が湧いた方は是非是非ご相談や体験にお越しください!
BodyMakeStudio100mile.では、こんなサポートができます。
・骨格ベクトレ(骨格レベルで姿勢改善を促す施術)
・リラクゼーション筋膜リリース(癒着した筋膜を動かし、バランスを整える)
・お家でできるセルフメンテナンス講座(自分で自分をメンテナンスする術をお伝えします)
・パーソナルトレーニング(適切な栄養バランスの計算や筋トレだけでなく、アジリティ、姿勢改善のメニューもご提案できます)
・エンジョイボクシング(ストレス発散、楽しく有酸素運動!)
BodyMakeStudio100mile.では様々な角度から、お身体の状況を考え、プランをご提案させて頂きます!
こちらの記事をご覧頂いた皆様が、ご自身のお身体を大切に、人生が充実することを祈っております!
メニュー紹介
ボディメイクスタジオ100マイルは深谷駅徒歩10分・駐車場完備のパーソナルジムです。骨格の歪みを整える施術と安全で継続しやすいトレーニングで肩こり腰痛の改善やボディメイク、ダイエットをサポートします。
脳神経科学パーソナルシークレットギャラリー
説明すると長くなりますので『こんなこともあるのか!』くらいにご覧頂ければと思います!
ご自身にとってどんなことが必要なのか、理屈と共に知りたい方は是非お問い合わせください!https://youtu.be/SF...
脳神経科学とは?
最新の疼痛生理学から派生した考え方『threat neuro matrix theory(脅威の神経配列))という理論をベースに、眼や皮膚感覚刺激、複雑なエクササイズを行うことで
・痛み
・...
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
脳神経科学を応用した動画ギャラリー
ご興味がありましたら是非ご覧頂き、身体の反応を確かめてみて下さい!...
エンジョイボクシング(動くボディメイク)
BodyMakeStudio100mile.のエンジョイボクシングは『楽しく動いて』脂肪燃焼や体力向...
骨格ベクトルトレーニング(動かないボディメイク)
心と身体が一致しないと身体は不調を訴え、心は落ち着かなくなります。Bod...
このコラムを書いた人
深谷のパーソナルジム・100マイル代表 後藤貴明

取得資格
- adidasパフォーマンストレーナー
- NSCA-CPT
- 骨格ベクトルトレーニング認定インストラクター
- Functional Neuro Training BASIC
など
メッセージ
パーソナルジムでの運動や施術が初めての方でもご安心ください!
それぞれのお身体に合わせた運動および、手技をご提供させて頂きます!
体験トレーニングのご案内
ボディメイクスタジオ100マイルでは手軽に当パーソナルジムのパーソナルトレーニングを体験して頂けるよう体験トレーニング(75分・5,500円)を行っております。
お気軽にお申し込みください。
TEL.080-5049-8607
※ご予約以外の営業等のご連絡は全てメールで対応とさせて頂きます。
※セッション中はお電話に出られない場合がございますので折り返させて頂きます。
パーソナルトレーニング 100mile.コラムに関連する記事
トレーニング?筋膜リリース?骨格ベクトレ?神経科学? その道の変態的お店のこだわりとは?
今回の記事は最近マニアック過ぎて、『変態レベル』と呼ばれ始めてきた当店のこだわりのご紹介になります。
お店をオー...
整体や治療院で教えてくれない神経科学の視点での肩こり・腰痛改善方法
今回の記事は少々難しい内容になるかもしれません。
というのも、整体や治療院などに通って『すぐに完璧に良くなった』...
VENEXリカバリーウェアがメンタルおよび人生を変える可能性を考察
今回の記事は当店で販売を開始した【VENEXリカバリーウェア】の秘めた可能性について考察した記事になります。
私...