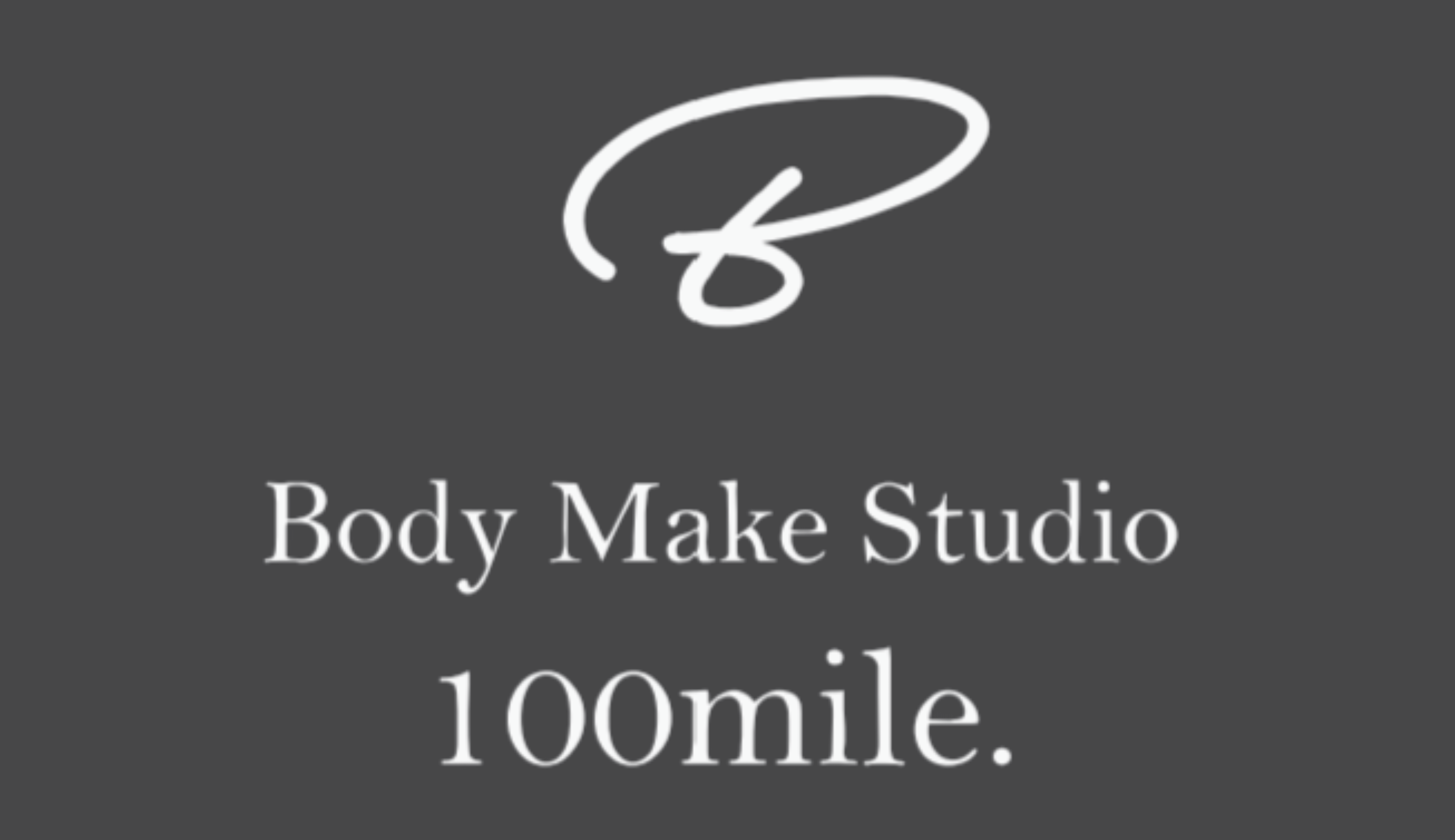皆さんこんにちは!BodyMakeStudio100mile.の後藤です!
前回の記事に続き、今回も肩こりや腰痛の内容を取扱いと思います。
肩こりや腰痛をお抱えの人は『姿勢が悪いから姿勢改善頑張らなきゃ!』と思い、筋トレやストレッチをに精を出して頂くことと思うんですが、今回は少々マニアックないわゆる【盲点】になりがちな内容をご紹介していけたらと思います。
読んでいて、『え!?そんなことが関係しているの!?』とか思う方もたくさんいらっしゃることと思いますし、実際自分の身体に置き換えてチェックしてみたら『ほんとだ!!』なんて発見もある内容となっておりますので
是非最後までお読みください!!
それでは参りましょう!

肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8案外知られていない姿勢改善方法
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8早速ランキング発表
早速ランキングについて発表していきます!
※結構知られていないことも多いかと思いますので、そんなことが??なんて思われる方もいらっしゃる内容もあるかと思います!
8位. 感情のクセを解放する(身体的アンカーの解放)
姿勢は“感情の履歴書”とも言われるほど、心の状態を映し出します。
怒り・不安・我慢のクセが筋肉や呼吸のパターンに現れることも。
深呼吸やトラウマからの解放ワークで、自然な姿勢が戻ることもあります。
7位. 歯列・噛み合わせのチェック
噛み合わせがずれると、顎の位置がズレて首や背骨にも影響が。
食いしばりや無意識のクセが、姿勢の歪みを引き起こすことも多いです。
歯科と連携したボディワークも今後注目される分野の一つです。
6位. 仙骨(尾てい骨上)の角度を微調整する
仙骨は“姿勢の羅針盤”のような存在で、ここが傾くだけで全身が崩れます。
逆に微調整するだけで、自然に上半身がスッと起き上がる感覚に。
骨盤の前傾・後傾の感覚を養うワークが効果的です。
5位. 腸腰筋の活性化
姿勢保持において超重要なインナーマッスル、腸腰筋。
ここが眠っていると、腰痛・猫背・足の疲れやすさにもつながります。
正しい起こし方を知ると、座ってるだけでも体幹が安定します。
4位. 後頭下筋群のリリース
首の付け根・頭のすぐ下の小さな筋肉たち。眼精疲労・ストレートネックの温床。
ここの緊張をゆるめると、視界が開けて呼吸もスッと楽になります。
手技やセルフリリースで、驚くほど体感が変わるポイントです。
3位. 足指の可動性を取り戻す
地面との接点である足指が固まっていると、姿勢全体が崩れやすくなります。
“踏ん張る力”が抜け、膝や腰で無理をするクセが出てしまいます。
足のワークは地味だけど、全身のバランス感覚に大きな影響。
2位. 眼球の動きを鍛える(眼トレ)
人は“目の向く方向”に自然と体を傾けます。
眼筋が固まっていると、首や肩の緊張も強くなります。
視線を自由に動かせることで、身体の動きも自由になります。
1位. 舌の位置を「上あご」に置く
姿勢の中でも盲点になりやすい“舌の位置”は、実は全身の土台。
上あごに自然に舌がつくと、顎・首・背骨が連動して整いやすくなります。
いつでもできる超シンプルな習慣で、驚くほど体の軸が変わります。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ88位. 感情のクセを解放する(身体的アンカーの解放)
「肩こり」や「腰痛」に悩まされている方は非常に多いですが、実はその根本原因が感情のクセにあることをご存知でしょうか?そして、その感情のクセが姿勢の歪みとして現れ、慢性的な肩こりや腰痛を引き起こしていることも少なくありません。
たとえば、緊張すると無意識に肩をすくめてしまったり、怒りをグッとこらえると奥歯を噛みしめて背中が固くなったり、悲しみがあると猫背気味になって胸が閉じてしまう。これらはすべて「身体的アンカー」と呼ばれる、感情と身体の結びつきのクセです。
■ 感情は筋肉を通して姿勢に刻まれる
人間の身体はとても正直です。
「我慢」「怒り」「不安」「悲しみ」などの感情を抱え込むと、それに反応して筋肉が緊張すると言われています。しかもこの緊張が一時的ではなく、無意識に長期間続くことで「悪い姿勢」として定着していくなんてことも。
悪い姿勢が続くと、筋肉のバランスが崩れて肩や腰に余計な負担がかかります。
こうして、感情→姿勢の歪み→肩こり・腰痛という流れができあがってしまいます。
つまり、姿勢改善のカギは“感情の解放”にあるとも言えるのです。
■ 「身体的アンカー」の例と影響
緊張 ⇒ 肩がすくむ・呼吸が浅くなる ⇒ 肩こり・胸郭の硬化
怒り ⇒ 噛みしめ・背中の緊張 ⇒ 首・肩のこわばり
悲しみ ⇒ 胸が閉じる・背中が丸まる ⇒ 猫背・腰への負担
不安 ⇒ 呼吸が浅くなり下腹部が緊張 ⇒ 骨盤が後傾し腰痛に
このように感情と身体はつながっており、それを解消することで肩こり・腰痛の予防や改善につながると言われています。
■ 解放のためにできる3つのアプローチ
1. 呼吸を深める(とくに横隔膜と骨盤底筋)
深い呼吸を意識すると、副交感神経が優位になり、心も体もリラックスします。
特に横隔膜がしっかり動くと、姿勢も自然と整いやすくなり、腰痛や肩こりも緩和されていきます。
2. 感情を抑え込まない(マインドフルネス・ジャーナリング)
ポジティブな感情も、ネガティブな感情も、感情を感じること自体にOKを出すと、身体の防御反応もゆるみます。
「今、自分は何を感じてる?」と自分に問いかけてみるようにしましょう。姿勢も呼吸も、自然にゆるみ始めます。
3. トラウマ・ストレスの身体的リリース(TREなど)
震えやあくび、深いため息など、身体の自然な反応に身を任せることで、深層にたまった緊張が解放されます。
これはまさに「身体的アンカーの解除」と言える作業で、姿勢改善にも直結すると言われています。
■ 姿勢改善とは「心と体の対話」
肩こりや腰痛をただストレッチや筋トレで改善しようとする前に、「自分はどんなネガティブな感情を無意識に身体にためているのか?」という視点を持ってみることをお勧めします。
そしてその感情をそっと見つめ、呼吸とともに手放すことで、自然と姿勢が整い、肩こり・腰痛も軽減されていくことにつながるかもしれません。
感情のクセをゆるめることは、姿勢改善だけでなく、人生の質そのものを整える入り口でもあります。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ87位. 歯列・噛み合わせのチェック
「肩こり」や「腰痛」に悩む人の多くが、歯列や噛み合わせに問題を抱えていることをご存知でしょうか?
実は、歯並びや噛み合わせは姿勢改善と深く関係しており、意外な盲点になりがちな領域です。マッサージやストレッチをしても肩こりや腰痛がなかなか改善しない場合、根本原因が“口の中”にある可能性もあるのです。
■ なぜ噛み合わせが姿勢に影響するのか?
口は体の中でも“中枢”に近い場所であり、頭蓋骨・顎・首・背骨と密接につながっています。
噛み合わせがズレていると、顎が左右どちらかに偏り、首の筋肉や背骨のバランスが崩れる原因になります。その結果、片方の肩に負担がかかり、慢性的な肩こりに。さらに、重心のズレが骨盤に伝わり、腰痛を引き起こすことも。
また、噛み合わせが悪いと頭の位置がズレやすくなり、首を前に突き出すような猫背姿勢になりがちです。これがまた、肩こりや腰痛の悪循環を生んでしまいます。
つまり、噛み合わせの乱れは“姿勢の土台”を崩す大きな要因とも言えます。
■ 肩こり・腰痛を引き起こす「噛みクセ」の例
食事中、いつも同じ側で噛んでいる
口を閉じた時、上下の歯の接触に左右差がある
就寝時、無意識に歯ぎしりや食いしばりをしている
口を開けるとカクッと音が鳴る、まっすぐ開かない
いつも唇が乾いていて、口呼吸になっている
これらの癖は、噛み合わせのズレや歯列のアンバランスのサインです。
こうしたクセがあると、体は自然とバランスをとろうとして、肩や腰に余計な力を入れて補正しようとします。それが長年続くことで、肩こり・腰痛が慢性化につながっていきます。
■ 噛み合わせのセルフチェック法(簡易)
口を軽く閉じてみて、上下の歯の当たり方に偏りがないか確認
鏡を見ながら口をゆっくり開けて、顎がまっすぐ動くか観察
ガムを左右均等に噛めているか意識してみる
就寝後、朝起きたときに顎の疲労感がないか確認
舌の位置が上あごに自然に収まっているか意識する
もし違和感や左右差を感じた場合、姿勢に影響している可能性が高いと考えられます。
■ 姿勢改善とセットで行いたい“口まわりケア”
肩こり・腰痛に悩んでいる方は、以下のような習慣を取り入れることをお勧めします。
就寝時の「食いしばり防止テープ」やマウスピースの使用
顎まわりのストレッチ(あいうべ体操など)
舌の位置を上あごにつけるトレーニング(舌筋トレ)
歯科医院での噛み合わせチェックやナイトガード相談
これらのケアは、直接的に噛み合わせを整えるだけでなく、姿勢を正しく保つための“口の筋肉バランス”を整える効果も期待できます。
その結果として、肩こりや腰痛の根本改善にもつながっていきます。
■ 歯列と噛み合わせは「姿勢の指令塔」
歯や噛み合わせの微妙なズレは、自覚しづらいですが、体のバランスに大きな影響を与える“司令塔”のような存在です。
姿勢が乱れれば肩こりや腰痛が発生し、さらにその不調が噛み合わせを悪化させるという“悪循環”が生まれます。
しかし逆に言えば、噛み合わせを整えるだけで、姿勢が自然と整い、肩こり・腰痛も改善される可能性もあるのです。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8ランキング6位~4位
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ86位. 仙骨(尾てい骨上)の角度を微調整する
あなたは「仙骨(せんこつ)」という骨を意識したことがありますか?
仙骨とは、骨盤の中心にある逆三角形の骨で、ちょうど尾てい骨の上にある土台のような骨です。実はこの仙骨の角度こそが、「肩こり」「腰痛」と深く関係しており、姿勢改善の隠れたカギでもあります。
■ 仙骨は“姿勢の芯”を支える重要パーツ
仙骨は、背骨の一番下にあり、骨盤の中央に位置しています。
この仙骨の角度が前に傾きすぎたり、逆に後ろに倒れすぎたりすると、背骨全体のカーブに影響を与え、上半身の姿勢バランスが崩れてしまうのです。
その結果、
上半身の重心がズレて肩に負担がかかり「肩こり」を引き起こす
背骨や腰椎のアーチが崩れて「腰痛」を誘発する
骨盤が不安定になり、全身の「姿勢改善」が難しくなる
つまり、仙骨のわずかな角度が、全身の姿勢バランスを左右する土台になっているのです。
■ 肩こり・腰痛の原因になる仙骨の“角度ミス”
現代人に多いのが、「仙骨が後ろに倒れてしまっている状態(骨盤後傾)」です。
これは長時間のデスクワークやスマホ姿勢、柔らかすぎるソファなどによって、座った姿勢のまま仙骨が後方に寝てしまっている状態です。
この状態になるとどうなるかというと…
骨盤が寝る→腰が丸まる→猫背になる→肩が前に出る→肩こり
腰の自然なアーチが失われる→腰椎にストレス→腰痛
重心が後ろにズレる→前ももやふくらはぎで立とうとする→全身疲労→姿勢悪化
こうした悪循環を防ぐには、仙骨の角度を正しく保つことが重要なのです。
■ 正しい仙骨角度とは?
理想的な仙骨の角度は、立っているときにやや前傾している状態(前傾30度前後)です。
これは骨盤を軽く立てているようなイメージで、背骨のS字カーブが自然に保たれる角度です。
逆に、仙骨が後傾すると背中が丸まりやすく、仙骨が過度に前傾すると反り腰になりやすくなります。
どちらも肩こり・腰痛の原因となるため、微妙な角度の「調整」が必要です。
■ 姿勢改善のための仙骨アプローチ方法
以下のようなアプローチで、仙骨の角度を整えることができます
① 正しい座り方を身につける
・椅子に座るときは、お尻を後ろに引き、坐骨で座るように意識
・背もたれに頼らず、仙骨の“縦の軸”を感じるイメージを持つ
・骨盤が立つ感覚をキープすることで、肩こりや腰痛の予防につながる
② 重心を整える立ち方を習得
・かかと重心になりすぎないよう、足裏全体で立つ意識
・膝をロックせず、柔らかく保つことで仙骨も自然と正しい位置に収まりやすくなる
■ 「姿勢改善=仙骨調整」くらいに考えてOK
肩こり・腰痛の原因は、局所的な筋肉の硬さだけでなく、身体の構造バランスの乱れにあることが多いです。
その構造バランスの“起点”になり得るのが、仙骨でもあります。
だからこそ、姿勢改善を真剣に考えるなら、まず仙骨の角度から見直すことも非常に効果的です。
仙骨が安定すれば、背骨・肩・首・頭の位置も整い、自然と肩こり・腰痛が軽減していくことにも繋がります。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8 5位. 腸腰筋の活性化
「腸腰筋(ちょうようきん)」という筋肉をご存知ですか?
これは、背骨(腰椎)と骨盤、太ももの骨(大腿骨)をつないでいる、インナーマッスルの中でも、とてもメジャーな筋肉です。
この腸腰筋を活性化することは、肩こり・腰痛の改善、そして姿勢改善にとって非常に重要な鍵になります。
■ 腸腰筋とは?なぜ姿勢と関係があるの?
腸腰筋は、「腸骨筋(ちょうこつきん)」と「大腰筋(だいようきん)」、「小腰筋(しょうようきん)」の総称です。
この筋肉は、骨盤の内側から背骨の前面を通って、太ももの内側につながっており、体幹の奥深くに位置するインナーマッスルです。
この腸腰筋が正常に働いていると、
骨盤が安定しやすくなり、腰への負担が減る → 腰痛予防
上半身を自然に起こしやすくなり、姿勢が美しくなる → 姿勢改善
背骨が整いやすくなり、肩に余計な力がかからない → 肩こり軽減
つまり、腸腰筋は下半身と上半身をつなぐ中心軸とも言える存在で、姿勢改善には欠かせない筋肉です。
■ 肩こり・腰痛と腸腰筋の関係
デスクワークや長時間の座り姿勢が続く現代人にとって、腸腰筋は固まりやすい・サボりやすい筋肉です。
腸腰筋が硬くなる、または弱くなることで以下のような不調が起こります:
骨盤が後傾し、猫背姿勢になりやすくなる → 肩こり悪化
腰椎の前弯が崩れ、腰に負担が集中する → 腰痛発生
立っているときの重心バランスが崩れる → 全体的な姿勢の崩れ
つまり、腸腰筋のコンディションが悪いと、肩こり・腰痛・姿勢改善すべてにマイナスの影響が出ると言えます。
■ 腸腰筋を活性化させるとどうなるか?
腸腰筋が目覚めると、体は本来あるべき位置に戻ろうとします。
骨盤が正しく立ち、腰のアーチが自然になる → 腰痛予防
背筋がスッと伸びて、猫背が改善される → 姿勢改善
背中や肩の筋肉に余計な力が入らず、リラックスできる → 肩こり軽減
特に女性は、ヒールやバッグの影響で骨盤がズレがち。男性は腹圧の低下から腰に負担がかかりやすいので、どちらも腸腰筋の活性化は有効です。
■ 姿勢改善のための腸腰筋トレーニング
以下に、肩こり・腰痛の改善にも効果的な「腸腰筋活性エクササイズ」を紹介します。
① 仰向け足上げ(レッグレイズ)
仰向けに寝て、片足ずつゆっくりと天井に向けて持ち上げる
腰が反らないように腹筋に軽く力を入れる
呼吸を止めずに、ゆっくり下ろす(左右10回ずつ)
② ランジポジション・腸腰筋ストレッチ
片足を前に出してランジ姿勢をとり、後ろ脚の腸腰筋を伸ばす
骨盤を前に軽く押し出すようにして20~30秒キープ
背筋は伸ばし、腹筋に力を入れて反り腰にならないよう注意する
■ 姿勢改善は「芯から整える」のがコツ
肩こりや腰痛に悩む多くの人が、マッサージやストレッチで表面の筋肉ばかりをケアしがちですが、盲点になる部分が「芯=腸腰筋」です。
インナーの筋肉が活性化すれば、外側の筋肉に無理な負担がかからず、自然と正しい姿勢を維持できるようになります。
特に長時間同じ姿勢をとる人ほど、腸腰筋を“使えていない”時間が長いため、肩こり・腰痛に悩まされやすいので注意が必要です。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ84位. 後頭下筋群のリリース
「肩こり」「腰痛」「姿勢改善」と聞くと、多くの人は背中や骨盤、脚の筋肉を連想しますが、実は首の付け根にある小さな筋肉群が、これらの悩みと密接に関係しているのをご存知でしょうか?
その筋肉群こそが「後頭下筋群(こうとうかきんぐん)」で見落とされがちですが、ここをゆるめるだけで肩こり・腰痛の大幅な改善が期待でき、姿勢改善へとつなげることができます。
■ 後頭下筋群とは?
後頭下筋群とは、頭と首をつないでいる4つの小さな筋肉の総称です。
具体的には、以下の筋肉が含まれます
・大後頭直筋
・小後頭直筋
・上頭斜筋
・下頭斜筋
これらの筋肉は、目線の安定・頭の位置調整・首の微細な動きを支えています。
つまり、後頭下筋群は、姿勢の「最終調整装置」とも言えるほど重要な役割を果たしているのです。
■ 姿勢が悪いと、後頭下筋群がガチガチに
スマホ首、猫背、長時間のデスクワーク。これらの悪姿勢が続くと、頭が前に突き出した状態になります。
すると、重たい頭を支えるために、後頭下筋群が常に緊張し続けることになります。
この緊張が続くと…
肩がすくむ・首が詰まる感覚 → 慢性的な肩こり
背中を丸めて頭を支えようとする → 姿勢の悪化
頭の位置がズレて背骨全体に負担がかかる → 腰痛に発展
つまり、後頭下筋群のこわばりが、肩こり・腰痛・姿勢の崩れの起点になっているケースも相当数あります。
■ 後頭下筋群をリリースするメリット
後頭下筋群をゆるめる(リリースする)ことで、次のような効果が期待できます
首と肩の余計な緊張がとれ、肩こりがスッと軽くなる
頭が正しい位置に戻り、背骨のS字カーブが自然に整う → 姿勢改善
重心が安定し、骨盤や腰への負担が減る → 腰痛予防にもつながる
さらに、ここには自律神経や眼精疲労とも関係する神経が多く分布しており、後頭下筋群をゆるめることでリラックス効果も期待できます。
■ 自分でできる!後頭下筋群のセルフリリース
① テニスボール or リリースボールを使う
仰向けに寝て、後頭部のくぼみにボールを2個並べてセット
深く呼吸しながら、ボールに頭の重みをゆっくり預ける
そのまま1~2分、微細なうなずき動作を加えると◎
② 指圧でやさしくほぐす
両手の指を後頭部のくぼみに当て、軽く圧をかける
顎を少し引き、後頭部を指に押し返すようにして10秒キープ
深呼吸とセットで行うと、よりリラックスできます。
③ 眼球運動とセットで整える
視線を上下左右にゆっくり動かすと、後頭下筋群が連動して緩みやすくなる
スマホの見すぎで固まった目と首を同時にケアできる
■ 姿勢改善で「頭の位置」の視点を持つことは大切
世の中の多くの「姿勢改善」法は、骨盤や腹筋などに注目されたものが多くあります。
もちろんそれも大切ですが、頭の位置を整えずに体幹だけ鍛えても、姿勢は本質的に変わらないケースも多くあります
なぜなら、重たい頭が前に出たままでは、どれだけ下半身が強くても、
その重さを支えるために背中や肩が緊張し、肩こり・腰痛が再発しやすいからです。
だからこそ、後頭下筋群のリリースは見落とされがちな改善方法なのです。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8ランキング3位~1位
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ8 3位. 足指の可動性を取り戻す
足指の可動性を取り戻すことも、肩こりや腰痛の根本改善、そして全身の姿勢改善にも直結する非常に大切なアプローチの一つです。
■ 足指と姿勢の関係とは?
足指は、私たちの身体の最下部にある土台です。
この小さな部位が柔軟に動き、しっかり地面をつかむことができていないと、重力に対して安定して立つことができず、全身のバランスが崩れます。
足指の可動性が低下すると
体の重心がズレて、腰や背中に負担がかかる → 腰痛の原因に
地面をしっかり踏みしめられず、体幹が緊張しやすくなる → 姿勢の悪化
バランスが崩れて肩に力が入り、肩こりが慢性化する → 肩こりの助長
つまり、足指が動かないことで姿勢全体が不安定になり、肩こり・腰痛の悪循環を生んでしまうことにつながります。
■ 足指が動かなくなる現代人の生活
クッション性の高い靴やインソール
デスクワーク中心の生活での足裏刺激不足
筋肉の使い方の偏り(浮き指・外反母趾)
これらの要因によって、多くの現代人は「足指が本来の機能を失っている」状態に陥ります。
特に浮き指や指が地面につかないクセがあると、立っているときに無意識のうちに体が前のめりになり、腰や肩の緊張につながっていきます。
■ 足指の可動性が回復すると起こる変化
足裏のセンサーが活性化し、重心バランスが整う → 姿勢改善
地面を踏みしめる力が生まれ、骨盤が安定 → 腰痛が軽減
上半身がリラックスし、肩周りの緊張が緩和 → 肩こり改善
足指をしっかり動かせるようになるだけで、不思議と姿勢が自然と整ってくることにつながります。
■ 肩こり・腰痛に効く!足指可動トレーニング
ここでは、簡単で効果的な足指トレーニングを紹介します。足が浮指で姿勢改善を目指す方は、ぜひ日常に取り入れてください。
① タオルギャザー
床にタオルを置き、足指で手繰り寄せる
片足ずつ行い、1日2〜3分から始める
足裏アーチを整え、腰痛・肩こりに効く土台作りにお勧めです
② 足指グーチョキパー体操
足指で「グー(握る)」「チョキ(2本だけ伸ばす)」「パー(全開)」をゆっくり繰り返す
指先の神経が目覚め、姿勢制御が改善されやすくなる
姿勢改善には、毎日習慣化するのがコツです
■ 姿勢改善は「下から整える」のも有効!
体幹や肩周りの筋トレももちろん大切ですが、それだけでは根本改善は難しい場合があります。
立ち方が変われば、歩き方が変わる。
歩き方が変われば、重心が変わる。
重心が変われば、肩こりも腰痛も自然とラクになる。
この変化は、上から押し付けるような「姿勢矯正」ではなく、足元から自然に起こる姿勢改善になります。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ82位. 眼球の動きを鍛える(眼トレ)
あまり知られていませんが「眼トレ(目のトレーニング)」を取り入れることで、肩こり・腰痛を和らげ、姿勢改善に大きな効果をもたらすことが期待できます
■ 目と姿勢の密接な関係私たちの身体は、目から得た情報をもとにバランスを取っています。
日頃私たちは目の位置や動きによって、脳が「今、自分がどんな姿勢で立っているのか」を判断しています。
例えば、以下のような現象が起こりがちです:
長時間スマホやパソコンを見ていると、目の筋肉が固まり視線が固定
結果として、首が前に出る「ストレートネック」に → 姿勢悪化
姿勢が崩れると、肩こり・腰痛のリスクが一気に高まる
つまり、「目の動きが悪い=姿勢が崩れる=肩こり・腰痛の悪化」というつながりがあるのです。
■ なぜ目を鍛えると肩こり・腰痛が改善するのか?
眼球を動かす筋肉(外眼筋)は、頭と首の深層筋と密接につながっています。
眼球の可動域が狭くなると、無意識のうちに首を傾けたり肩に力が入るような動きで補おうとします。
その結果…
目を動かすたびに首が動いてしまう → 肩こり・首こりが慢性化
視野が狭くなり、バランスが崩れる → 姿勢が悪くなり腰痛が出る
頭の位置がズレて背骨に無理がかかる → 姿勢全体が歪む
逆に言えば、眼球の動きをスムーズにしてあげるだけで、自然と首や肩の力が抜けて姿勢が整い、腰にも優しい身体に変わっていく効果が期待できます。
■ 姿勢改善に効果的な眼トレ(目の体操)をご紹介!
① ゆっくり眼球だけを動かすトレーニング
頭を動かさず、視線だけで上下・左右・斜めを見る
1方向につき3秒ずつキープ、1セット×3周ほど繰り返す
目の筋肉が目覚め、姿勢保持力が自然にアップ
② ペン先トラッキング(寄り目の運動)
ペンを顔の前に持ち、ゆっくりと近づけたり遠ざけたり
目のピント調整力が高まり、目の奥の緊張が和らぐ
肩こりの原因となる目の疲れがスッキリ解消!
③ 視野を広げる「周辺視野」トレーニング
視線は前に向けたまま、左右の指を動かして見る
周辺視野を使うことで、脳のバランス機能が活性化
姿勢がふらつかず、腰痛の原因となる“無意識の偏り”が減少
■ 眼トレは「静かなコアトレ」でもある
眼球の動きは、実は頭部・頸椎・骨盤の連動に深く関係しています。
目線が正しく動けば、無理な補正動作が減り、姿勢改善が加速します。
これは筋肉を鍛えるというより、感覚と神経のトレーニングに近いイメージです。
派手な動きではありませんが、実際には全身の姿勢制御に強い影響を与えるマニアックかつ本質的なアプローチと言えます。
■ 肩こり・腰痛に悩む人こそ“目をゆるめて使う”意識を
肩こりや腰痛が慢性化している方は、「目の使い方が常に緊張状態」であることが多いです。
一点を凝視したり、無意識に目を見開いていたりすることが、肩や背中に力を入れ続ける原因になります。
目の筋肉が固まると、脳や自律神経も緊張モードに。
だからこそ、目をリラックスさせて動かすことが、肩こり・腰痛の根本的な姿勢改善につながるのです。
肩こり・腰痛に効果的、マニアックな姿勢改善方法トップ81位.舌の位置を「上あご」に置く
「肩こり」「腰痛」「姿勢改善」に取り組んでいる方にとって、筋トレやストレッチは定番ですが、実はもっと根本的で繊細な改善ポイントが「舌の位置」です。
舌をどこに置いているか? それだけで、全身の姿勢バランスが変わり、肩こり・腰痛の原因を根本から取り除くことが可能になるのです。
■ 舌の位置と姿勢の不思議な関係
私たちが無意識に置いている「舌の位置」は、実は首・顎・頭の位置、さらには骨盤にまで影響を与えています。
特に、舌が「下あご側」に落ちている状態は、頭の重心が前にズレることを意味します。
このとき起こる反応は、
頭が前に出る(=猫背の原因)
首が緊張し、肩こりが悪化
背骨全体のS字カーブが崩れて、腰痛リスクがアップ
つまり、「舌の位置」が悪いだけで、肩こり・腰痛が慢性化し、姿勢改善が進みにくくなるのです。
■ 正しい舌の位置とは?
理想的な舌のポジションは、「上あごの前歯の裏側から奥まで舌全体がピタッとくっついている状態」です。
ポイントは、舌の先端だけではなく「舌全体」を上あごに密着させること。
この状態を「正しい舌位(ぜつい)」と呼びます。
このポジションを保てると、
首や顎の筋肉がリラックスし、肩こりの軽減につながる
頭の位置が中心に戻り、猫背改善・姿勢改善が進む
噛みしめ癖の予防や、睡眠の質の向上にもつながる
まさに、全身の「静かな支点」なのです。
■ 舌が下がるとどうなる?肩こり・腰痛との関係
舌が下あごに落ちている状態では、無意識に口呼吸が優位になり、次のような連鎖が起きます
口呼吸 → 首が前に出る
首が前に出る → 肩が内巻きになり、巻き肩になる
肩が内巻き → 背中が丸くなり、腰が反る or 丸まる
腰の負担が増え → 腰痛が慢性化
つまり、舌の位置の崩れが、肩こり・腰痛を引き起こす姿勢崩壊のスタート地点になることもあるわけです。
■ 舌を「上あご」に置くトレーニング法
・ 舌リフト・トレーニング
口を閉じ、舌を上あごにできるだけ広く当てる
舌全体で軽く「押す」ような意識で10秒キープ
1日10回、毎日継続する
このトレーニングを行うだけで、顔面〜頭部〜頸椎の連動がスムーズになり、姿勢改善の促進が期待できます。
・ 発声を使った方法(「ンー」の音)
「ンーー」と鼻に抜ける音を出すと、自然に舌が上あごにくっつきます。
これは発声と姿勢を同時に整えるセルフトレーニングとして有効です。
■ 舌の位置を整えることはインナーポスチャーを整えること
舌は、体の中でもっとも深層にある「姿勢センサー」の一部です。
舌の位置を整えることで、身体の軸が整い、肩こり・腰痛が根本から改善するような“内側の支え”が生まれます。
表面の筋肉ではなく、内側から支える力が育つため、長期的で安定した姿勢改善が可能になるのです。
■ 姿勢改善のゴールは“無意識の質を上げる”ことに在り
本質的な肩こり・腰痛の解消や姿勢改善は、「正しい姿勢を頑張って保つこと」ではなく、「自然に正しい姿勢になっている状態」を作ることです。その起点となり得るのが「舌の位置」。
つまり、舌を上あごに置くことを習慣化すれば、無意識でも首や背中に負担のない姿勢が身につき、肩こりや腰痛が起こりにくい身体に変化していくのです。
肩こり、腰痛に湿布は本当に効くのか考えるまとめ
いかがでしたでしょうか?
身体の繋がりに驚嘆した方も多いのではないでしょうか?
1+1=2 みたいに簡単なら良いのですが、残念ながら人間の身体はもっと複雑な関係性や繋がりで成り立っています。
逆に言えば、肩こりや腰痛の解消方法や、姿勢改善について取れる対処方法は沢山ありますので、いくつか試して上手くいかなかったからと言って『一生このまま』なんて絶望に打ちひしがれることはないんです。
様々な角度からご自身の身体をチェックして、トライして、反応を見て、良い反応のものを見つける&継続してみることで解消することがほとんどですので、是非名探偵になった気分でご自身の身体を解き明かしていきましょう。
BodyMakeStudio100mile.では、こんなサポートができます。
・骨格ベクトレ(骨格レベルで姿勢改善を促す施術)
・リラクゼーション筋膜リリース(癒着した筋膜を動かし、バランスを整える)
・お家でできるセルフメンテナンス講座(自分で自分をメンテナンスする術をお伝えします)
・パーソナルトレーニング(適切な栄養バランスの計算や筋トレだけでなく、姿勢改善のメニューもご提案できます)
・エンジョイボクシング(ストレス発散、楽しく有酸素運動!)
BodyMakeStudio100mile.では様々な角度から、お身体の状況を考え、プランをご提案させて頂きます!
こちらの記事をご覧頂いた皆様が、ご自身のお身体を大切に、人生が充実することを祈っております!
メニュー紹介
ボディメイクスタジオ100マイルは深谷駅徒歩10分・駐車場完備のパーソナルジムです。骨格の歪みを整える施術と安全で継続しやすいトレーニングで肩こり腰痛の改善やボディメイク、ダイエットをサポートします。
脳神経科学とは?
最新の疼痛生理学から派生した考え方『threat neuro matrix theory(脅威の神経配列))という理論をベースに、眼や皮膚感覚刺激、複雑なエクササイズを行うことで
・痛み
・...
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
脳神経科学を応用した動画ギャラリー
ご興味がありましたら是非ご覧頂き、身体の反応を確かめてみて下さい!...
エンジョイボクシング(動くボディメイク)
BodyMakeStudio100mile.のエンジョイボクシングは『楽しく動いて』脂肪燃焼や体力向...
骨格ベクトルトレーニング(動かないボディメイク)
心と身体が一致しないと身体は不調を訴え、心は落ち着かなくなります。Bod...
100mile.コース(動かない×動くボディメイク)
健康を維持していくためには身体を動かすことと、整えることの双方必要になります。...
このコラムを書いた人
深谷のパーソナルジム・100マイル代表 後藤貴明

取得資格
- adidasパフォーマンストレーナー
- NSCA-CPT
- 骨格ベクトルトレーニング認定インストラクター
- Functional Neuro Training BASIC
など
メッセージ
パーソナルジムでの運動や施術が初めての方でもご安心ください!
それぞれのお身体に合わせた運動および、手技をご提供させて頂きます!
体験トレーニングのご案内
ボディメイクスタジオ100マイルでは手軽に当パーソナルジムのパーソナルトレーニングを体験して頂けるよう体験トレーニング(75分・5,500円)を行っております。
お気軽にお申し込みください。
TEL.080-5049-8607
※ご予約以外の営業等のご連絡は全てメールで対応とさせて頂きます。
※セッション中はお電話に出られない場合がございますので折り返させて頂きます。
パーソナルトレーニング 100mile.コラムに関連する記事
トレーニング?筋膜リリース?骨格ベクトレ?神経科学? その道の変態的お店のこだわりとは?
今回の記事は最近マニアック過ぎて、『変態レベル』と呼ばれ始めてきた当店のこだわりのご紹介になります。
お店をオー...
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?
今回の記事は中高年の方に向けた内容になります!
最近セミナーなどもたくさん実施していますが、その先々でお話しする...
整体や治療院で教えてくれない神経科学の視点での肩こり・腰痛改善方法
今回の記事は少々難しい内容になるかもしれません。
というのも、整体や治療院などに通って『すぐに完璧に良くなった』...