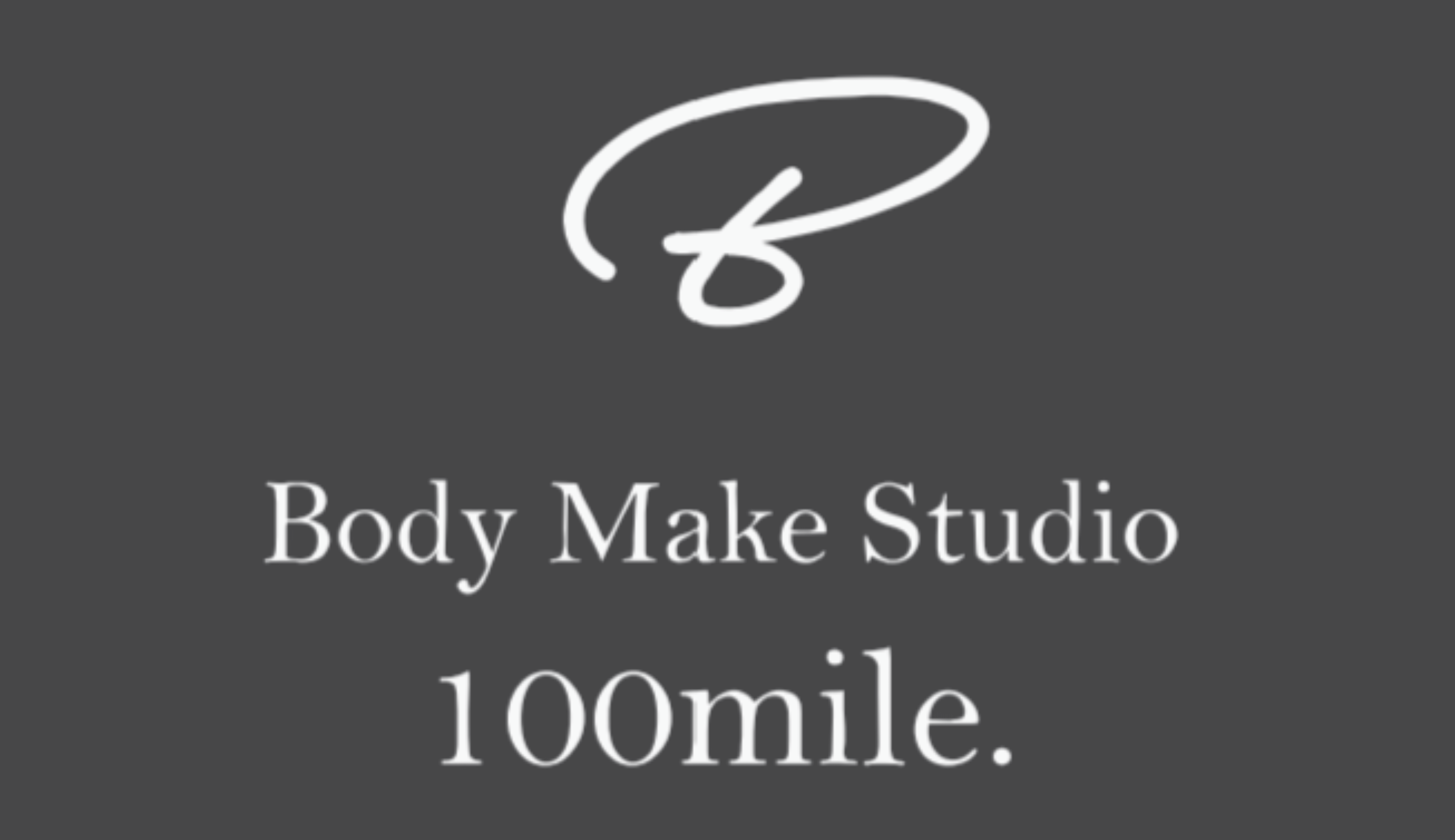皆さんこんにちは!BodyMakeStudio100mile.の後藤です!
この記事を読んでいただいている方の多くには、肩こりや腰痛を感じ、姿勢を良くしたいと思う方が多いのではないでしょうか?
今回は姿勢を改善するためにはトレーニング、筋膜リリースのどちらか一方ではなく、両方組み合わせることで、姿勢改善がよりスピーディーに進むということについてご紹介したいと思います。
姿勢改善の方法は様々ありますが、運動が好きな方はトレーニングに偏ったり、運動が苦手な方はストレッチや筋膜リリースに偏りがちです。
偏りなく行って頂く為にも、是非そのメリットを見ていきましょう!

トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!姿勢が崩れるのは「硬さ」と「弱さ」の両方が原因
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!猫背や反り腰などの姿勢の乱れは、筋膜の癒着と筋力の低下が関係している
現代社会において、多くの人が猫背や反り腰といった姿勢の乱れに悩まされています。
その主な原因の一つとして、筋膜の癒着と筋力の低下が関与していることが挙げられ、筋膜リリースやトレーニングを通じたアプローチが姿勢改善に有効であることは広く認識されていますが、そもそも筋膜の癒着と筋力の低下がどのように姿勢に影響を及ぼすのかを理解することが重要です。
筋膜は筋肉を包み込み、組織同士の滑らかな動きを助ける役割を果たしています。
しかし、長時間の不良姿勢や運動不足、過度の負荷などにより筋膜は癒着を起こしやすくなります。
筋膜が癒着すると、筋肉の伸縮がスムーズに行われず、特定の筋群が過度に緊張したり、逆に使われにくくなったりします。例えば、デスクワークなどで前傾姿勢が続くと、胸部の筋膜が硬くなり、背中の筋肉は引き伸ばされた状態が続きます。これにより、猫背の姿勢が固定化され、正常な筋バランスが崩れてしまいます。
また、反り腰の場合、骨盤前傾が過剰になり、大腿四頭筋や脊柱起立筋の緊張が増す一方で、腹筋やハムストリングスなどの筋力が低下することで姿勢が維持できなくなります。筋膜の癒着が生じることで、これらの筋群のアンバランスがさらに助長され、骨盤の歪みが固定化されます。その結果として、腰椎への負担が増し、慢性的な腰痛や筋疲労を引き起こす要因となります。
筋力の低下も姿勢の乱れに大きく関与しています。筋力が低下すると、適切な姿勢を維持するための筋肉のサポートが不十分になり、体が楽な姿勢を取ろうとします。その結果、無意識のうちに筋膜の癒着が進行し、不良姿勢が習慣化されていきます。
特にインナーマッスルの弱化は姿勢に直結しやすく、体幹の安定性が失われることで、猫背や反り腰が悪化する原因となります。
筋膜の癒着と筋力低下が姿勢の乱れを引き起こすメカニズムは、単なる筋肉の問題ではなく、全身の連鎖的な影響によるものです。筋膜は全身を覆うネットワークとして働き、一部の癒着が他の部位にも影響を及ぼします。
例えば、足部の筋膜の硬直が骨盤の歪みにつながり、それがさらに脊柱全体のバランスを崩すこともあります。そのため、姿勢の改善には局所的なアプローチではなく、筋膜リリースやトレーニングを組み合わせた包括的な視点が必要となります。
このように、姿勢の乱れは筋膜の癒着と筋力の低下が相互に作用し合うことで生じます。したがって、筋膜リリースやトレーニングを通じて、筋膜の柔軟性を取り戻し、適切な筋力をつけることが姿勢改善の鍵となります。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!硬い部分をほぐすだけでは正しい姿勢を維持できない
姿勢改善のための手法として「筋膜リリース」が注目されていますが、筋膜リリースのみでは正しい姿勢の維持が難しいです。
これは、筋膜リリースが一時的な筋肉の柔軟性向上に寄与するものの、姿勢を支える筋力や神経筋のコントロールが不足しているためです。
筋膜は全身を包む結合組織であり、筋肉や関節の動きをスムーズにする役割を果たしています。長時間の同じ姿勢や不適切な体の使い方によって筋膜が癒着すると、動きの制限や痛みを引き起こします。筋膜リリースは、これらの癒着を解消し、筋肉の可動域を向上させる効果があります。
しかし、筋膜リリースだけでは姿勢の根本的な改善にはつながりません。なぜなら、姿勢を維持するためには、筋膜の柔軟性だけでなく、適切な筋力バランスや神経系の働きが不可欠だからです。筋膜が柔らかくなっても、それを支える筋力がなければ、正しい姿勢を長時間維持することは難しくなります。
正しい姿勢を維持するには、特定の筋肉群が適切に働く必要があります。特に、体幹(コア)の筋肉や肩甲骨周りの安定性を高める筋肉が重要な役割を果たします。これらの筋肉が十分に働いていなければ、筋膜リリースで一時的に可動域が改善されたとしても、時間の経過とともに元の状態に戻りやすくなります。
また、筋膜リリースの効果を最大限に引き出すためには、筋肉の適切な収縮・弛緩のサイクルが必要です。筋膜リリース後に適切な筋力トレーニングを行うことで、筋肉の機能を向上させ、姿勢を安定させることができます。
筋膜リリースの効果を持続させるためには、単に筋力をつけるだけでは不十分であり、神経筋の制御能力を高めることも求められます。神経と筋肉の協調が取れていない状態では、筋肉が適切なタイミングで働かず、結果的に姿勢の乱れを引き起こしてしまいます。
神経筋とは、神経系と筋肉が連携して体をスムーズに動かす仕組みのことを指します。神経が筋肉に適切な指令を送ることで、必要な筋肉が正しく働き、適切な姿勢を維持することができます。しかし、この神経筋の働きが低下すると、本来使うべき筋肉がうまく機能せず、他の筋肉に負担がかかることで姿勢が崩れてしまいます。神経筋の制御を向上させることで、筋肉が適切に働き、無理なく正しい姿勢を維持しやすくなります。
例えば、デスクワークが多い人は、肩が内側に巻き込みやすく、胸の筋膜が硬くなる傾向があります。この状態を改善するために筋膜リリースを行い、可動域を広げたとしても、肩甲骨周りの筋肉が適切に機能しなければ、すぐに元の姿勢に戻ってしまいます。したがって、筋膜リリース後に適切なエクササイズを行い、正しい姿勢を脳と体に覚えさせることが重要です。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!弱い部分を鍛えるだけでは動きがスムーズにならない
姿勢改善を目的としたトレーニングを行う際に、単に弱い筋肉を鍛えるだけでは効果が十分に得られません。
これは、姿勢の崩れが単なる筋力不足ではなく、筋膜の状態や筋肉のバランスの乱れによって引き起こされるためです。
筋膜リリースなどを行わずにトレーニングだけを実施すると、強張った筋肉が動きを妨げ、姿勢改善につながらないばかりか、むしろ誤った姿勢が固定化されてしまう可能性があります。
姿勢改善には、筋肉だけでなく筋膜の状態も大きく関わっています。筋膜は筋肉を包み込み、全身の動きを統合する役割を持っていますが、長時間の不良姿勢や偏った動作が続くと、筋膜が癒着し、特定の筋肉が過剰に緊張した状態になります。この状態のままトレーニングを行うと、筋膜の制限によって関節の可動域が狭まり、鍛えたい筋肉が十分に動けず、姿勢改善にはつながりません。
例えば、猫背の状態で背中のトレーニングを行っても、前側の筋膜が硬くなったままでは肩甲骨の動きが制限され、背筋の力を適切に発揮できなくなります。
また、姿勢改善には筋肉のバランスが重要ですが、トレーニングのみでこのバランスを整えることは難しい場合があります。筋膜の癒着や筋肉の強張りがあると、本来動くべき筋肉が適切に機能せず、代償動作が生じます。例えば、腰を反らせるクセがある人が腹筋を鍛えようとしても、腹筋ではなく腰の筋肉に負担がかかるため、本来の目的とは異なる筋肉ばかりが発達してしまいます。
筋膜リリースを行わずにトレーニングを続けると、このような誤った動作パターンが強化され、姿勢改善どころか、さらなる不調を引き起こすことになりかねません。
さらに、姿勢改善のためには、脳が正しい姿勢を認識し、適切な筋肉を使うことが必要です。しかし、筋膜が硬くなり、筋肉の動きが制限されていると、身体が誤った姿勢を「正しい」と認識してしまい、トレーニングを行っても不適切な姿勢が定着してしまいます。
特に長年の姿勢のクセがある場合、筋膜リリースを行わずにトレーニングを行うと、無意識のうちに元の悪い姿勢のまま力を入れるクセがついてしまい、姿勢改善にはつながらないのです。
このように、筋膜リリースを行わずにトレーニングだけで姿勢改善を試みても、強張った筋肉が動きを制限し、正しい姿勢を身につけることが難しくなります。姿勢改善には、単に弱い筋肉を鍛えるのではなく、筋膜の状態を整え、全身の筋肉が正しく機能する環境をつくることが必要です。
筋膜の癒着で動きに制限がある状態でトレーニングを行っても、姿勢改善にはつながらず、誤った動作パターンが固定化される可能性があるため、鍛えるだけでは不十分なのです。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!筋膜リリースで姿勢改善がスムーズになる理由
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!筋膜は全身を覆い、姿勢のバランスを左右する存在
筋膜は全身を覆い、姿勢のバランスを大きく左右する重要な組織です。筋膜は単なる筋肉の覆いではなく、筋肉同士をつなぎ、力の伝達や身体の安定性を保つ役割を担っています。
筋膜の状態が姿勢改善に大きく影響を与えるのは、筋膜が全身にわたって連続性を持ち、筋肉や関節の動きと密接に関わっているためで、筋膜の柔軟性や滑走性が失われると、トレーニングを行っても適切な姿勢改善が進みにくくなります。
筋膜は「第2の骨格」とも言われるほど、姿勢改善において重要な役割を果たします。筋肉単体ではなく、筋膜を介して全身の筋肉がつながっているため、ある部位の筋膜が硬くなると、その影響が離れた部位の姿勢バランスにまで及びます。
例えば、足底の筋膜が硬くなると、ふくらはぎや太もも、さらには骨盤の位置まで変化し、最終的には背中や首の姿勢にまで影響を及ぼします。このように、筋膜の状態が全身の筋肉や骨格の配置に影響を与えるため、トレーニングを行う際にも筋膜のバランスを考慮しなければ、正しい姿勢改善は実現できません。
また、筋膜はテンセグリティ構造と呼ばれる特性を持ち、全身のバランスを保つ重要な役割を果たしています。テンセグリティとは、張力と圧縮力のバランスによって構造が安定する性質のことであり、人体においては筋膜がこのバランスを維持する働きをしています。
筋膜の一部が過剰に緊張すると、その張力が周囲の筋肉や関節に影響を与え、姿勢バランスが崩れてしまいます。例えば、デスクワークによって前側の筋膜が硬くなると、胸や肩が内側に引っ張られ、猫背の姿勢が定着してしまいます。この状態でいくらトレーニングを行っても、筋膜の制限があるために適切な姿勢改善が難しくなります。
※テンセグリティ構造を理解するには、テントをイメージするとわかりやすいかと思います。テントの中央に立てる支柱を骨とした場合、支柱にかぶせる布は筋膜で、かぶせた布(筋膜)を四方から均等に引っ張る事でテントは立ちますが、どこかが極端に引っ張る力が強かったり、どこかが全く引っ張らなかった場合はテントは崩れます。それは骨や筋膜で置き換えた人体構造でも同じ現象が起こるということです。
さらに、筋膜は神経や血管とも密接に関係しており、その状態が姿勢改善だけでなく、運動機能全般に影響を及ぼします。
筋膜には多くの感覚受容器が存在し、姿勢のフィードバック機能(姿勢が崩れている、正しいなどの脳への報告)を担っています。そのため、筋膜が硬くなると身体の固有感覚が鈍くなり、正しい姿勢を認識しにくくなります。例えば、猫背の人が背筋を伸ばそうとしても、筋膜が硬くなっていると「伸ばしすぎ」と誤認し、元の不良姿勢のほうが楽に感じることがあります。このように、筋膜の状態が脳と身体の連携に影響を与え、姿勢改善の妨げとなることがあります。
トレーニングによって筋力を強化することは姿勢改善に役立ちますが、筋膜のバランスが乱れていると、狙った筋肉を適切に使うことができません。筋膜が硬くなることで可動域が制限され、トレーニングの動作が本来の筋力発揮のメカニズムから逸脱してしまうことさえあります。
例えば、股関節周りの筋膜が硬くなっている場合、スクワットの際に膝や腰に過剰な負担がかかり、本来鍛えたい部分ではなく、別の筋肉に力が入りやすくなります。その結果、トレーニングによって姿勢改善を試みても、間違った動作パターンが強化されることになりかねません。
※補足としてトレーニングに限らず、日常的な動作も含め、ある目的を達成するために、特定の関節の動きが悪い場合、他の関節が必要以上に大きく動いて動作を補完するということが起きます。
(『床に落ちたものを拾う』という行為を行う際に、股関節の動きが悪いとその分、膝や足首の関節が大きく動いて補完するため、負担もかかりやすくなる)
筋膜は単なる筋肉の覆いではなく、全身の張力を調整し、姿勢のバランスを維持する重要な組織です。
そのため、姿勢改善には筋膜の柔軟性や滑走性を考慮しながらトレーニングを行うことが必要になります。筋膜の状態が乱れると、トレーニングによる筋力強化が十分に活かされず、むしろ姿勢の崩れを助長してしまうこともあります。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!硬くなった筋膜が動きを制限し、悪い姿勢を引き起こす
筋膜は全身を覆い、筋肉や骨格の動きをスムーズにする役割を担っています。しかし筋膜が硬くなると、動きが制限され、姿勢改善が難しくなる他、トレーニングのみでは姿勢改善が難しい理由について解説いたします。
①長時間の同じ姿勢や偏った動作が続く
・デスクワークやスマートフォンの使用により、長時間同じ姿勢を続ける。
・片側の肩にばかりバッグをかける、足を組むなどの習慣で、特定の部位に負担がかかる。
・運動不足や特定の筋肉ばかりを使う偏ったトレーニングが、姿勢のバランスを崩す要因となる。
⇒特定の部位に継続的な負担がかかり、筋膜が硬くなり始める
②筋膜が癒着し、滑走性が低下する
・筋膜は本来、筋肉同士の間を滑らかに動くように機能するが、長時間の同じ姿勢により癒着しやすくなる。
・筋膜の滑走性が低下すると、筋肉の伸び縮みが制限され、可動域が狭くなる。
・血流やリンパの流れが悪くなり、筋膜自体がさらに硬くなりやすくなる。
⇒筋膜の動きが悪くなり、筋肉のスムーズな動作が阻害される
③動きが制限され、代償動作が生じる
・硬くなった筋膜の影響で、本来動くべき筋肉がうまく機能しなくなる。
・その結果、別の筋肉が本来の役割以上に働く代償動作が起こり、姿勢改善が難しくなる。
・例えば、股関節周りの筋膜が硬くなると、骨盤の動きが制限され、腰や膝に負担がかかる。
・肩甲骨周りの筋膜が硬くなると、肩の可動域が狭まり、首や背中の筋肉が過剰に緊張する。
⇒筋膜の硬さが全身に影響を及ぼし、姿勢の歪みが生じる
④筋膜の硬さが姿勢改善を妨げる
・動きが制限されることで、無意識のうちに体のバランスを取ろうとし、誤った姿勢が定着する。
・例えば、背中の筋膜が硬くなると、猫背の姿勢になりやすい。
・骨盤周りの筋膜が硬くなると、反り腰や左右のバランスの崩れが生じる。
・肩や首の筋膜が硬くなると、巻き肩やストレートネックの姿勢になりやすくなる。
⇒筋膜の硬さが原因で、正しい姿勢が維持できなくなる
⑤姿勢改善が困難になり、筋膜の硬さが進行する
・一度崩れた姿勢が習慣化すると、脳がその姿勢を「正しい状態」と誤認する。
・悪い姿勢のまま日常生活を送ることで、特定の部位に負担が集中し、筋膜がさらに硬くなる。
・筋膜の硬さが悪化すると、適切なトレーニングを行っても姿勢改善が難しくなる。
⇒姿勢の悪化と筋膜の硬直が悪循環を引き起こし、身体の柔軟性が低下する
⑥トレーニングの効果が低下する
・筋膜が硬くなると、筋肉が適切に動かないため、トレーニングの効果が十分に発揮されない。
・可動域が制限された状態でトレーニングを行うと、誤ったフォームが定着し、姿勢改善が進まない。
・特定の筋肉だけが過剰に働くことで、さらに筋膜が硬くなりやすくなる。
⇒筋膜の状態を無視したトレーニングでは、姿勢改善につながらない可能性がある
上記の様なスパイラルに陥ると、なかなかトレーニングだけで姿勢改善を促すことは難しくなるため、筋膜リリースを取り入れることがとても重要になります。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!まず筋膜の癒着を取り除くことで、身体が本来の状態に戻りやすくなる
筋膜の癒着を取り除くことで、身体の動きがスムーズになり、姿勢改善が促進されます。筋膜は筋肉や関節と密接に関わっているため、筋膜の柔軟性が回復することで、適切な姿勢を維持しやすくなります。
特に、筋膜リリースによって筋膜の滑走性を向上させることは、トレーニングの効果を高めるだけでなく、姿勢改善にも大きく寄与します。ここでは、筋膜の癒着を取り除くことでどのように身体が本来の状態に戻るのか、そのメカニズムを詳しく説明します。
①筋膜リリースによる滑走性の回復
筋膜リリースを行うことで、筋膜の滑走性が回復し、筋肉や関節が本来の可動域を取り戻しやすくなります。筋膜の癒着があると、特定の筋群が過度に緊張し、逆に別の筋群が適切に機能しなくなることがあります。この状態が続くと、姿勢のバランスが崩れ、動作の制限が生じます。
筋膜リリースによって筋膜の癒着を取り除くと、筋肉の動きがスムーズになり、必要な部位が適切に働くようになります。その結果、姿勢改善が促され、トレーニング時のフォームも正しく維持しやすくなります。また、筋膜の滑走性が向上することで、筋肉同士の協調性が改善され、トレーニング効果の向上につながります。
②筋膜リリースによる張力の均等化
筋膜は全身に張力を伝達する役割を持ちます。筋膜の癒着が発生すると、特定の部位に張力が集中し、アンバランスな負担かかることで姿勢が崩れます。筋膜リリースを行うことで、筋膜全体の張力が均等に分散されるようになります。これにより、特定の部位に過剰な負担がかからなくなり、身体全体のバランスが整います。その結果、姿勢改善が進み、トレーニング時の動作も安定しやすくなります。特に、筋膜の癒着が解消されることで、筋肉の適切な収縮・弛緩が可能になり、トレーニングの効果が最大化されます。
③筋膜リリースによる感覚フィードバックの正常化
筋膜には多くの神経受容器が存在し、身体の位置や動きを脳に伝達する役割を担っています。筋膜が癒着すると、神経受容器の働きが低下し、身体のバランス感覚が狂いやすくなります。その結果、誤った姿勢が「正常な姿勢」として認識され、無意識のうちに悪い姿勢が定着してしまいます。
筋膜リリースを行うことで、神経受容器の機能が正常化され、脳が正しい姿勢を認識しやすくなります。これにより、意識しなくても適切な姿勢を維持しやすくなり、姿勢改善が進みます。また、トレーニング時にも正しいフォームを維持しやすくなり、怪我のリスクが軽減されるだけでなく、より効率的に筋力を向上させることができます。
④筋膜リリースがトレーニング効果を向上
筋膜の癒着を取り除くことで、トレーニングの効果も大きく向上します。筋膜リリースによって筋肉の可動域が広がることで、適切な筋活動が促され、ターゲットとする筋肉を効果的に鍛えることができます。
また、筋膜の滑走性が回復することで、トレーニング時のフォームが安定し、無駄な力を使わずに効率的な動作が可能になります。これにより、姿勢改善が進むだけでなく、トレーニングの効果も向上し、弱化していた筋肉も強化しやすくなります。
さらに、筋膜の柔軟性が向上すると、神経と筋肉の協調性が改善され、よりスムーズな動作が可能になります。これにより、トレーニング中のパフォーマンスが向上し、正しい姿勢を維持しながら運動を行うことができます。
⑤筋膜リリースと姿勢改善の関係
筋膜の癒着は、姿勢の乱れや動作の制限を引き起こす大きな要因の一つです。筋膜が硬くなることで可動域が制限され、筋肉のバランスが崩れ、結果的に誤った姿勢が定着してしまいます。
しかし、筋膜リリースを行うことで、滑走性の回復、張力の均等化、感覚フィードバックの正常化といった生理的な変化が起こります。これにより、筋肉や関節が本来の動きを取り戻し、正しい姿勢を維持しやすくなります。
また、筋膜の状態が改善されることで、トレーニングの効果も向上し、より効率的に姿勢改善を進めることができます。
したがって、トレーニングだけでなく姿勢改善のためには筋膜リリースが重要であり、筋膜の状態を整えることが弱化した筋肉のトレーニング効果を高めるためにも不可欠です。筋膜リリースを継続的に行うことで、身体が本来の状態に戻り、より健康的で機能的な姿勢を維持できるようになります。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!トレーニングで姿勢改善がスムーズになる理由
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!筋肉のバランスが整う
トレーニングは、筋肉のバランスを整え、姿勢を改善する上で重要な役割を果たします。
筋肉は相互に拮抗しながら働き、骨格を適切な位置に保持します。しかし、特定の筋肉が過緊張(縮んで硬くなる)し、逆に別の筋肉が弱化(緩み弱くなる)すると、筋肉のバランスが崩れ、姿勢の歪みが生じます。これを修正するためには、トレーニングを通じて筋肉のバランスを調整し、適切な筋活動を促すことが必要です。
1. 拮抗筋のバランス調整による姿勢安定
筋肉は「拮抗筋」として対を成しながら機能します。例えば、ある筋肉が収縮する際、反対の筋肉は伸張されるという関係性を持ちます。この拮抗筋のバランスが崩れると、骨格の位置が乱れ、姿勢不良を引き起こします。特に、長時間の同じ姿勢や反復動作によって、特定の筋肉に過剰な負荷がかかると、拮抗筋のバランスが大きく崩れます。
トレーニングによって過緊張している筋肉の活動を適正化し、弱化している筋肉を強化することで、拮抗筋のバランスを回復することができます。これにより、筋肉が均等に機能し、骨格が本来の位置へと調整され、正しい姿勢を保持しやすくなります。
2. 神経筋制御の最適化と姿勢調整
姿勢は筋肉の単独の働きだけでなく、神経系による制御によっても維持されています。長期間にわたる不良姿勢は、神経筋制御に影響を与え、誤った筋活動パターンを脳が学習してしまう要因となります。そのため、筋肉のバランスを改善するには、適切な神経筋制御の再構築が不可欠です。
トレーニングによって適切な筋活動パターンを習得すると、脳が正しい姿勢を維持するための神経信号を発しやすくなります。これにより、特定の筋肉に過度な負荷がかかることを防ぎ、全身の筋肉がバランスよく働くようになります。また、適切な神経筋制御によって、日常的に無意識のうちに正しい姿勢を保持しやすくなります。
3. 筋肉の協調性向上と姿勢安定
筋肉は単独で機能するのではなく、複数の筋群が協調しながら働くことで姿勢を保持しています。この筋肉の協調性が低下すると、特定の筋群に負担が集中し、姿勢の崩れが生じます。トレーニングによって筋肉の協調性を向上させることで、全身の筋肉が適切に機能し、姿勢の安定性が向上します。
また、筋肉の協調性を高めることで、姿勢維持のための無駄なエネルギー消費を抑えることができます。これにより、長時間の姿勢維持が容易になり、疲労しにくい身体へと変化します。
4. 体幹筋の活性化と姿勢改善
姿勢の安定には、体幹筋の適切な機能が不可欠です。体幹筋は脊柱や骨盤を安定させる役割を持ち、姿勢を支える基盤となります。しかし、体幹筋の活動が低下すると、姿勢の維持が困難となり、他の筋肉に過度な負担がかかることで、さらなる姿勢の崩れを引き起こします。
トレーニングによって体幹筋を適切に活性化することで、脊柱や骨盤の安定性が向上し、姿勢が改善されます。特に、体幹深部の筋肉を鍛えることで、姿勢保持のための筋活動が最適化され、無意識のうちに正しい姿勢を維持しやすくなります。
5. 姿勢を支える筋緊張の調整
筋肉の緊張は、姿勢を維持するために必要な要素ですが、過度な筋緊張は筋バランスを崩し、姿勢の歪みを引き起こします。特に、同じ筋肉が持続的に緊張し続けると、血流が悪化し、筋肉の柔軟性が低下することで、姿勢保持が困難になります。
トレーニングによって適切な筋緊張を維持し、過度な緊張を抑えることで、筋肉のバランスが最適化されます。これにより、姿勢の歪みが解消され、長時間の姿勢維持が容易になります。
6. 姿勢維持筋の耐久力向上
姿勢を維持するためには、筋持久力の向上も重要です。持久力の低い筋肉は、疲労しやすく、長時間の姿勢維持が困難となります。特に、脊柱起立筋や腹筋群などの姿勢維持に関与する筋肉の持久力が低下すると、正しい姿勢を長時間維持できなくなります。
トレーニングによって筋持久力を向上させることで、姿勢を崩さずに維持する能力が高まります。これにより、疲労による姿勢の崩れを防ぎ、長時間にわたって正しい姿勢を保持することが可能となります。
7. 動作の最適化と姿勢調整
姿勢は静的なものではなく、動作の連続によって維持されています。そのため、動作の最適化が姿勢改善において重要な要素となります。トレーニングによって正しい動作パターンを学習することで、姿勢を崩すことなく動作を行う能力が向上します。
また、日常生活の動作においても、トレーニングによる姿勢調整が有効に働きます。正しい筋活動パターンを習得することで、姿勢を維持しながら効率的な動作を行うことができ、無駄な負担を減らすことができます
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!関節可動域の向上
関節可動域が制限される要因には、筋膜の滑走性低下、筋肉の柔軟性低下、神経筋制御の不全などがあり、これらをトレーニングで改善することで、姿勢改善が促進されます。
1.筋膜への影響
筋膜は、筋肉や関節を包み込む結合組織であり、その滑走性が関節可動域に大きな影響を与えます。トレーニングによって筋膜の滑走性が向上すると、関節の動きがスムーズになり、姿勢改善が進みます。筋膜の滑走性が低下すると、関節の動きが制限され、代償動作が生じやすくなります。この状態では、関節可動域が狭まり、姿勢が崩れやすくなります。
また、筋膜には機械受容器が存在し、トレーニングによる適切な刺激が神経筋制御の適正化に関与します。これにより、筋膜の緊張が調整され、関節可動域の向上が期待できます。姿勢改善においても、筋膜の状態を整えることが重要であり、トレーニングによる筋膜の適応が関節の動きを改善する要因となります。
2. 筋肉への影響
トレーニングによって筋肉の柔軟性が向上すると、関節可動域の拡大が促進されます。特に、エキセントリック収縮を伴うトレーニングは、筋肉の伸張性を向上させ、関節の可動域を広げる効果があります。筋肉の柔軟性が低下すると、関節の動きが制限され、姿勢改善が妨げられますが、トレーニングによる適切な負荷を与えることで、筋肉が適応し、関節可動域の向上につながります。
筋肉は適応能力を持っており、トレーニングを継続することで最適な長さと張力を維持できるようになります。これにより、関節の動きがスムーズになり、無理のない姿勢を維持しやすくなります。また、トレーニングによって拮抗筋のバランスが整うと、関節の安定性が向上し、可動域がさらに拡大します。
3. 神経筋抑制への影響
関節可動域の向上には、神経筋制御の改善が不可欠です。神経筋制御とは、脳と筋肉が協調して運動を調整する仕組みであり、トレーニングによってこの機能が最適化されると、関節の動きが効率的になります。姿勢改善においても、適切な神経筋制御が重要であり、トレーニングによる神経伝達の改善が関節可動域の拡大に貢献します。
トレーニングによる繰り返しの動作が、脳と筋肉の協調性を高め、関節を最適な軌道で動かせるようになります。これにより、関節の可動域が広がり、姿勢改善がスムーズに進みます。また、関節の安定性が高まることで、不必要な筋緊張が抑制され、より自由な動作が可能となります。
4. 関節アライメントへの影響
関節の適切なアライメントを維持することは、関節可動域の向上に不可欠です。関節アライメントが崩れると、関節の動きが制限され、筋肉や筋膜のバランスが乱れます。トレーニングによって関節アライメントを適正化すると、関節の動きがスムーズになり、可動域が広がります。特に、姿勢改善においては、骨盤や脊柱のアライメントを整えることが重要であり、トレーニングを通じて関節の正しい位置を維持することで、可動域の向上が促進されます。
5. 筋出力への影響
関節可動域の向上には、筋出力の適正な調整が必要になります。筋出力が適切に調整されると、関節が無理なく動かせるようになり、可動域が拡大します。特に、拮抗筋のバランスが整うことで、関節の動作が安定し、姿勢改善が促されます。
また、筋出力の調整は、神経筋制御とも関連しており、トレーニングを通じて適切な神経伝達が確立されると、関節可動域が向上し、正しい姿勢を維持しやすくなります。これにより、姿勢改善が自然に進み、関節の可動性が高まることで、より効率的な動作が可能となります。
6. 動作学習への影響
関節可動域の向上には、正しい運動パターンの学習が不可欠です。トレーニングを通じて適切な動作を繰り返し行うことで、神経回路が強化され、関節の動きが最適化されます。姿勢改善においても、正しい運動パターンを習得することで、関節の適正な可動域を維持しやすくなります。
また、関節可動域が向上すると、動作の自由度が増し、姿勢の安定性が高まります。トレーニングを通じて適切な動作を身につけることで、筋肉や筋膜のバランスが整い、関節可動域の向上が持続的に進行します。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!神経系の適応と運動パターンの修正
トレーニングを続けることで、神経系の働きが変化し、体の動かし方が自然と修正されていきます。この仕組みは姿勢改善にも大きく関わります。神経系が適切に機能すると、体を無理なく正しく動かせるようになり、姿勢を維持しやすくなります。
1. 神経系の適応
トレーニングを行うと、脳と筋肉をつなぐ神経の働きが良くなり、指令がスムーズに伝わるようになります。この結果、体の動きが効率的になり、姿勢を正しく保つことがしやすくなります。
トレーニングを重ねることで、脳が「この動きが正しい」と学習し、次第に無意識でも適切な動きができるようになります。これが、運動パターンの修正につながります。
2. 神経と筋肉の連携
神経と筋肉は電気信号を通じてつながっています。トレーニングを行うと、この信号の伝わり方がスムーズになり、筋肉の動きが細かくコントロールされるようになります。これによって、必要な筋肉が適切に働き、姿勢の崩れを防ぐことができます。
また、筋膜リリースによって筋肉の緊張がほぐれると、神経の信号がより正確に伝わるようになり、動作のバランスが取りやすくなります。
3. 運動パターンの修正
運動パターンとは体が覚えている動きのクセのようなもので、トレーニングを行うことで、悪いクセが修正され、正しい動きが身につきます。これは、脳が新しい動きを学習し、神経のつながりを作り変えることで起こります。この変化は「シナプス可塑性」と呼ばれ、繰り返し正しい動きを行うことで強化されます。
4. 体の感覚と姿勢改善
私たちの体は、無意識のうちに姿勢を調整する機能を持っています。この機能を「体性感覚」といい、筋肉や関節が今どの位置にあるかを脳に伝える役割を果たします。
トレーニングを行うと、この体性感覚が正確になり、姿勢の崩れに気づきやすくなります。
※さらに筋膜リリースを行うと、筋膜内の感覚受容器が活性化し、体の状態をより正確に把握できるようになります。
5. 神経伝達と運動効率
神経がスムーズに働くことで、動きが無駄なく行えるようになります。トレーニングを続けると、神経の伝達速度が上がり、より素早く適切な筋肉を使えるようになり、この変化は姿勢の維持にも役立ちます。
※また筋膜リリースを取り入れることも筋膜の状態が整い、神経の働きがよりスムーズになります。その結果、トレーニングの効果が高まり、姿勢改善がより早く進みます。
6. 神経の変化と姿勢の定着
トレーニングを継続すると、神経のネットワークが強化され、正しい姿勢を無意識にキープできるようになります。神経は、繰り返し使われる回路を強化するため、姿勢改善のトレーニングを続けることで、良い姿勢が当たり前になります。
筋膜リリースと組み合わせることで、神経がよりスムーズに働き、姿勢改善がさらに進みやすくなります。
トレーニングと筋膜リリースの両立が姿勢改善のコツ!まとめ
いかがでしたでしょうか?
トレーニングにはトレーニングの、筋膜リリースには筋膜リリースの良い面を持っていて、姿勢改善には双方を組み合わせることがとても重要です!
中々運動できていない方は、軽いものでも良いので運動を、
動き過ぎて身体がメンテナンスできていない方はこれを機に、メンテナンスを
日常に取り入れてお身体を大切にしてみませんか?
BodyMakeStudio100mile.では、こんなサポートができます。
・骨格ベクトレ(骨格レベルで姿勢改善を促す施術)
・リラクゼーション筋膜リリース(癒着した筋膜を動かし、バランスを整える)
・お家でできるセルフメンテナンス講座(自分で自分をメンテナンスする術をお伝えします)
・パーソナルトレーニング(適切な栄養バランスの計算や筋トレだけでなく、姿勢改善のメニューもご提案できます)
・エンジョイボクシング(ストレス発散、楽しく有酸素運動!)
ご興味がありましたら、ぜひ一度お申し込みください!(精一杯サポートいたします!)
こちらの記事をご覧頂いた皆様が、ご自身のお身体を大切に、人生が充実することを祈っております!
メニュー紹介
ボディメイクスタジオ100マイルは深谷駅徒歩10分・駐車場完備のパーソナルジムです。骨格の歪みを整える施術と安全で継続しやすいトレーニングで肩こり腰痛の改善やボディメイク、ダイエットをサポートします。
脳神経科学パーソナルシークレットギャラリー
説明すると長くなりますので『こんなこともあるのか!』くらいにご覧頂ければと思います!
ご自身にとってどんなことが必要なのか、理屈と共に知りたい方は是非お問い合わせください!https://youtu.be/SF...
脳神経科学とは?
最新の疼痛生理学から派生した考え方『threat neuro matrix theory(脅威の神経配列))という理論をベースに、眼や皮膚感覚刺激、複雑なエクササイズを行うことで
・痛み
・...
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
具体的な事例内容を簡単にご紹介!筋膜リリース、骨格ベクトレ、トレーニング
脳神経科学を応用した動画ギャラリー
ご興味がありましたら是非ご覧頂き、身体の反応を確かめてみて下さい!...
エンジョイボクシング(動くボディメイク)
BodyMakeStudio100mile.のエンジョイボクシングは『楽しく動いて』脂肪燃焼や体力向...
骨格ベクトルトレーニング(動かないボディメイク)
心と身体が一致しないと身体は不調を訴え、心は落ち着かなくなります。Bod...
このコラムを書いた人
深谷のパーソナルジム・100マイル代表 後藤貴明

取得資格
- adidasパフォーマンストレーナー
- NSCA-CPT
- 骨格ベクトルトレーニング認定インストラクター
- Functional Neuro Training BASIC
など
メッセージ
パーソナルジムでの運動や施術が初めての方でもご安心ください!
それぞれのお身体に合わせた運動および、手技をご提供させて頂きます!
体験トレーニングのご案内
ボディメイクスタジオ100マイルでは手軽に当パーソナルジムのパーソナルトレーニングを体験して頂けるよう体験トレーニング(75分・5,500円)を行っております。
お気軽にお申し込みください。
TEL.080-5049-8607
※ご予約以外の営業等のご連絡は全てメールで対応とさせて頂きます。
※セッション中はお電話に出られない場合がございますので折り返させて頂きます。
パーソナルトレーニング 100mile.コラムに関連する記事
トレーニング?筋膜リリース?骨格ベクトレ?神経科学? その道の変態的お店のこだわりとは?
今回の記事は最近マニアック過ぎて、『変態レベル』と呼ばれ始めてきた当店のこだわりのご紹介になります。
お店をオー...
中高年が抱える不調の原因となる気づかないストレスとは?
今回の記事は中高年の方に向けた内容になります!
最近セミナーなどもたくさん実施していますが、その先々でお話しする...
整体や治療院で教えてくれない神経科学の視点での肩こり・腰痛改善方法
今回の記事は少々難しい内容になるかもしれません。
というのも、整体や治療院などに通って『すぐに完璧に良くなった』...